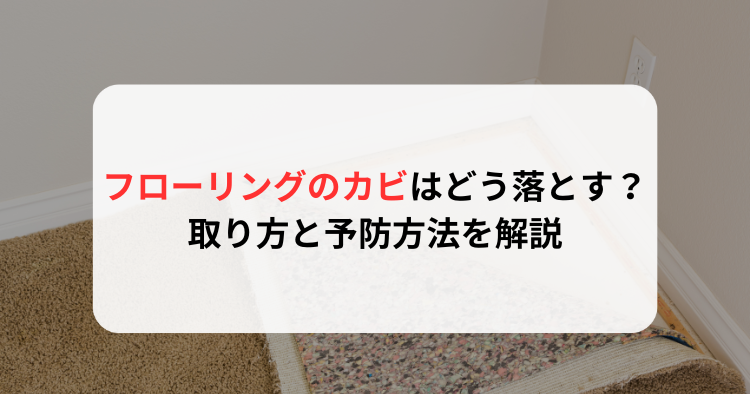フローリングにカビが生えているのを発見して、ゾッとしたことはありませんか?
カビは見た目の問題だけでなく、健康にも悪影響をおよぼす厄介な存在です。
本記事では、フローリングにカビが生える原因から、効果的な掃除方法、再発を防ぐための予防策を詳しく解説します。
最後まで読めば、フローリングのカビ問題を根本から解決できるようになるので、ぜひ最後までご一読ください。
【フローリングのカビ】家全体に広がってしまうかも?
「フローリングの黒カビ、何度掃除しても再発…」そんなお悩みはありませんか?
実は、目に見えないカビの胞子がすでに家全体に広がっている可能性も!
放置すると、アレルギー悪化・咳が止まらない・体調不良が続く など、健康被害の原因に。
当社では、カビの根本原因を特定し、再発防止まで徹底サポート!
市販品では落とせない床材の奥深くに根付いたカビを除去し、家族の健康と住環境を守ります。
最短即日対応・深夜・早朝もOK!プロに任せれば、一回の掃除で長期的にカビを防げます!
まずは無料でご相談ください!
専門技術 × 幅広い対応!特殊清掃・カビ除去・災害復旧・お片付け清掃もおまかせください!
目次
1.フローリングにカビが生える原因
フローリングにカビが生える原因として、以下の3点が挙げられます。
- 適度な温度
- 適度な湿度
- 栄養素
フローリングの場合、特に注意すべきなのが水分との接触です。
窓際の結露がフローリングに落ちたり、濡れたカーペットを長時間敷いたままにすると、フローリングが湿気を吸収してしまいます。
また、布団を敷きっぱなしにしていると、床との間に湿気がこもりやすくなります。
さらにフローリングに落ちた食べかすやペットフードなどの有機物も、カビの繁殖を加速させる要因です。
カビを予防するには、日常生活のなかで水分や汚れをこまめに取り除くことが求められます。
以下の記事では、床下に発生したカビの対処法についても解説しているので、併せてご確認ください。
床下にカビが生えている?現れる症状や原因は?対処法を詳しく解説
2.フローリングに生えたカビを落とす5つの手順
フローリングのカビを効果的に除去するには、以下の手順で清掃を行います。
- 窓を開けて換気する
- 中性洗剤で拭き掃除をする
- 溝のカビはつまようじで掃除する
- エタノールスプレーで仕上げ拭き
- 完全に乾かす
それでは、各手順の詳細を見ていきましょう。
手順1.窓を開けて換気する
フローリングのカビ掃除を始める前に、窓を開けて空気の流れを作ります。
1か所だけでなく対角線上にある窓を開けることで室内の空気が入れ替わり、効果的に換気を行えます。
窓が一か所しかない部屋では、換気扇やサーキュレーターを使って空気を動かしましょう。
ただし粉状のカビが付着している場合には、注意が必要です。
このような状況で窓を開けると、カビの胞子が部屋中に舞ってしまう危険性があります。
先に拭き掃除を済ませてから、換気を行うようにしましょう。
手順2.中性洗剤で拭き掃除をする
フローリングのカビを効果的に除去するには、汚れを浮かせる効果が高い中性洗剤を使用します。
頑固なカビがある場合は洗剤をかけたあとにラップで数分覆い、汚れをふやかしてから拭くと効果的です。
このとき注意するのは、カビ掃除に使用した雑巾は再利用せず、使い捨てにするということです。
雑巾にはカビの胞子が残っているため、使い回すと部屋中に胞子を拡げることになってしまいます。
捨てても良いウェスやペーパータオルなどを使うようにしましょう。
手順3.溝のカビはつまようじで掃除する
フローリングの溝は、黒カビが溜まりやすい場所なので、つまようじを使う方法が効果的です。
掃除手順は、以下のとおりです。
- つまようじの先端を溝に差し込みます。
- ゆっくりと溝に沿って動かし、カビを掻き出します。
- 掻き出したカビは、すぐにペーパータオルなどで拭き取ります。
古い歯ブラシや、100均で購入できる隙間ブラシを使うのも効果的です。
掻き出す際にカビが飛び散りやすいので、慎重に作業を行います。
また、掃除に使用した道具にはカビの胞子が付着しているため、つまようじやブラシはすぐに廃棄しましょう。
手順4.エタノールスプレーで仕上げ拭き
掃除の仕上げにエタノールスプレーを使うことで、より確実にカビを除去し、再発を防ぐことができます。
エタノールスプレーを使う手順は以下のとおりです。
- 洗剤が残らないよう水拭きで仕上げます。
- フローリングが完全に乾いたことを確認します。
- エタノールスプレーを適量で噴霧し、エタノールを染み込ませた清潔な布で拭き取ります。
エタノールスプレーはキッチン用の消毒スプレーで代用も可能です。
ただしフローリングによっては変色するため、目立たない場所でテストしてから使うことをおすすめします。
注意点として、エタノールスプレーは大量に使用し、約30秒間以上接触面に残留する程度の量を噴霧しましょう。
また、換気を十分に行いながら作業を進めることも大切です。
手順5.完全に乾かす
掃除が終わったら、部屋を十分に換気して完全に乾燥させます。
効果的な乾燥方法は以下のとおりです。
- 窓を全開にして十分な換気を行います。
- 風が通りにくい場合は、扇風機やサーキュレーターを使用して空気を循環させます。
- フローリングの溝までしっかりと乾燥させるため、時間をかけて乾かします。
湿気が残りやすいフローリングの溝もしっかり乾燥させましょう。
水分が残ったままだと、カビが再発する原因になります。
乾燥中は部屋に入らないようにし、ペットや子どもが濡れた床を踏まないよう注意しましょう。
また、以下の記事では自分で出来るカビの取り方を紹介しています。
自分でできるカビの取り方は?場所やおすすめのカビ取り剤、注意点まとめ
3.注意!カビ取りでやってはいけないこと
フローリングのカビ取りは、正しい方法で行わないと逆効果になります。
ここでは、カビ取りの際に絶対に避けるべき3つの行為を紹介します。
- 重曹を使う
- 塩素系漂白剤を使う
- 掃除機をかける
これらの方法はフローリングにダメージを与えたり、カビの被害を広げる可能性があります。
それぞれの理由と適切な対処法を詳しくみていきましょう。
注意1.重曹を使う
フローリングのカビ取りに重曹を使うのは避けましょう。
重曹は多くの掃除に活用される万能アイテムですが、フローリングには適していません。
特にワックスが塗られているフローリングでは、重曹によってワックス層が削られてしまい、床材の保護機能が失われます。
さらに深刻なのは、重曹で床材自体を傷つけてしまうことです。
傷ついた部分はカビの侵入口となり、かえってカビの被害を広げてしまいます。
一時的にカビが取れたように見えても、長期的には逆効果になりかねません。
床材を傷つけずに効果的にカビを除去できる方法を選ぶことが、フローリングの保護とカビの再発防止につながります。
注意2.塩素系漂白剤を使う
塩素系漂白剤の脱色作用は、カビだけでなくフローリングの素材自体も脱色してしまう危険性があります。
塩素系漂白剤によって脱色されたフローリングは、元の色に戻すことが困難です。
単なる見た目の問題だけでなく、フローリングの品質や耐久性にも影響を与える可能性があります。
市販のカビ取り洗剤には、塩素系のものが多くみられます。
必ず成分表示を確認したうえで、掃除の前に目立たない場所でテストを行うようにしましょう。
注意3.掃除機をかける
カビの生えたフローリングに掃除機をかけるのは絶対に避けましょう。
掃除機でカビを吸い込むと、カビの胞子が掃除機の排気口から放出され、室内全体に拡散してしまう危険性があります。
掃除機自体もカビの胞子で汚染されてしまい、別の場所にカビを広げてしまう可能性もあります。
同様の理由で、粉状のカビが大量に生えている場所で換気を行うのも避けるべきです。
換気によってカビの胞子が舞いあがり、室内に広がってしまう可能性があります。
掃除の際はマスクを着用するなど、胞子を吸わないようにする対策も必要です。
4.フローリングのカビを予防する5つの方法
フローリングのカビは根絶が難しく、環境が整えば再発することもあります。
ここでは、フローリングのカビを予防する5つの方法を紹介します。
- 除湿と換気をこまめに行う
- 布団やベッドは定期的に乾燥させる
- エタノールで拭き掃除をする
- カーペットを敷きっぱなしにしない
- 防カビワックスを塗布する
それでは詳細をみていきましょう。
方法1.除湿と換気をこまめに行う
カビの予防において、除湿と換気はもっとも重要なポイントのひとつです。
カビは気温20℃以上、湿度60%以上の環境で活性化します。
温度と湿度をコントロールするのが、カビ対策の基本です。
毎日最低30分、窓を開けて外気を取り入れることで、室内の湿気を効率的に排出できます。
梅雨時や湿気がたまりやすい場所では、除湿器の導入も検討しましょう。
除湿器は、室内の湿度を一定に保つのに役立ちます。
カビが生えやすい場所には、温湿度計を設置するのもおすすめです。
定期的に湿度をチェックしてカビが発生しやすい時期や場所を把握することで、重点的に対策を講じられます。
方法2.布団やベッドは定期的に乾燥させる
布団やマットレスは身体から出る汗を吸収するので、湿気がこもりやすい場所です。
壁やフローリングに密着していると、カビの温床になってしまいます。
予防のためには、定期的な乾燥が欠かせません。
晴れた日には外に出して天日干ししましょう。
太陽の紫外線には殺菌効果があり、布団やマットレスの湿気を効率よく飛ばすことができます。
天日干しが難しい場合は、布団乾燥機を使うのも良い方法です。
特に夏場は汗をかきやすいので、予想以上に布団やマットレスが湿っています。
こまめな乾燥を心がけましょう。
方法3.エタノールで拭き掃除をする
エタノールにはカビのタンパク質を固めて弱体化させる作用があるので、フローリングのカビ予防に効果的です。
エタノールを使う際の手順は以下のとおりです。
- エタノールを霧吹きに入れる、または清潔な布に含ませる
- フローリング全体を均一に拭く
- 水分が目立つは場合は拭き取る
ただしエタノールには脱色や脱水の作用があるため、フローリングの素材によっては傷める可能性があります。
使用前に目立たない場所でテストを行い、変色や損傷がないことを確認してから使用しましょう。
週に1〜2回程度の頻度で行うことで、カビの予防効果を維持しつつ、フローリングへの負担を最小限に抑えられます。
方法4.カーペットを敷きっぱなしにしない
カーペットはカビの温床になりやすい家具のひとつです。
カビの栄養源となる汚れや湿気を吸収しやすく、フローリングにも影響をおよぼす可能性があります。
カーペットのカビ予防には以下の対策が効果的です。
- 定期的に干して乾燥させる
- 可能であれば丸洗いやクリーニングに出す
- 洗濯機で洗えるタイプのカーペットを選ぶ
湿気の多い季節や雨の日が続くときは、カーペットを上げて床を乾燥させることが大切です。
ポイントはカーペットを「敷きっぱなし」にしないことです。
定期的にカーペットを上げてフローリングの状態を確認し、乾燥や清掃を行うことで、カビの発生リスクを大幅に減らすことができます。
方法5.防カビワックスを塗布する
フローリングのカビ予防において、防カビワックスの塗布は効果的な方法のひとつです。
市販のフローリングワックスのなかには、防カビ効果を謳った商品も多く販売されています。
この商品を使うことで、フローリングの傷や汚れを予防するだけでなく、カビの抑制効果も期待できます。
防カビワックスの使用方法は以下のとおりです。
- フローリングを十分に清掃し、乾燥させる
- 説明書にしたがって適量のワックスを塗布する
- 均一に伸ばし、完全に乾燥させる
防カビワックスを選ぶ際は、フローリングの素材に適したものを選ぶことが重要です。
ワックスは3〜6か月に1回程度の頻度で塗り直すことをおすすめします。
定期的なワックス塗布を習慣化することで、フローリングの美しさを保ちながら、カビの発生リスクを軽減できます。
以下の記事では、カビ臭い部屋の対処法やその原因、予防法についても解説しているので、併せてご確認ください。
5.カビを放置することで起きる健康被害について
フローリングのカビは見た目だけの問題だけでなく、深刻な健康被害をもたらす可能性があります。
カビは目に見えない胞子を空気中に放出し、喘息や気管支炎、アレルギー症状といった疾患を引き起こす原因になります。
高齢者や子ども、既往症のある人だけでなく、健康な大人も健康を害する可能性があるのです。
カビは放置しても、胞子が自然に死滅することはありません。
時間が経つにつれてカビの繁殖範囲が広がり、より多くの胞子が空気中に放出されるので、早めの対策が重要です。
6.賃貸でフローリングのカビが落ちない時は早めに管理会社へ
賃貸物件でフローリングにカビが発生し、自分で掃除しても落ちない場合は、早めに管理会社へ相談しましょう。
強く擦ったり、塩素系漂白剤を使用するとフローリングの表面が傷んだり変色したりする可能性があるからです。
また、カビの発生原因が建物の構造や環境による場合、入居者の責任ではなく、管理会社が対応するケースもあります。
例えば、換気が不十分な設計や結露が発生しやすい部屋では、適切な対策を講じてもカビが再発しやすく、根本的な問題は入居者側で解決できないことが多いです。
さらに、自己判断で間違った方法を使い、フローリングを傷めてしまうと、退去時に修繕費を請求される可能性もあります。
特に、強い薬剤やスチームクリーナーの使用はフローリングの塗装を剥がすリスクがあるため注意が必要です。
ですので、カビを見つけたらまずは写真を撮影し、管理会社に相談しましょう。
掃除の可否や適切な対処法を確認できるだけでなく、万が一建物側の問題が原因であれば、修繕や防カビ対策を管理会社が負担してくれることもあります。
自己判断で対処せず、早めに専門家に相談することが賃貸物件での適切な対応です。
7.フローリングのカビには早めの対策が肝心
フローリングのカビ問題は単なる見た目の問題と思われがちですが、実際はそれ以上に深刻な影響をもたらします。
長期間放置されたカビはフローリングの表面だけでなく、ワックスでコーティングされている内側にもカビが侵入する場合があります。
そうなると、表面を薬剤で清掃するだけではカビが除去できず、ワックスの剥離が必要になったり、場合によってはフローリングを腐食させ耐久性を著しく低下させる可能性があります。
さらに深刻なのは、カビが住人の健康に与える影響です。
カビの胞子は空気中を浮遊し、呼吸を通じて体内に入り込みます。
子どもや高齢者、既往症のある方にとって深刻な健康リスクとなり得るものです。
健康で快適な住環境を維持するためにも、フローリングのカビには早めの対策を行いましょう。
私たちSpread株式会社のコラムで取り上げている「カビ除去」に関する情報をまとめた記事が以下です。
家庭内のカビ対策から業者依頼、健康被害まで多様なテーマを紹介しています。
他にもカビに関する悩みがあれば、こちらの記事もチェックしてみてくださいね。