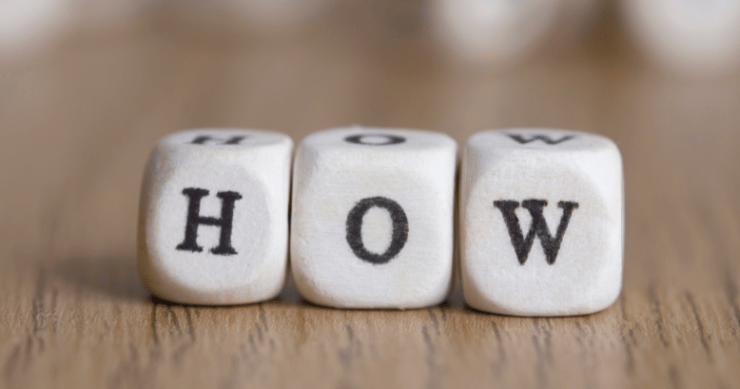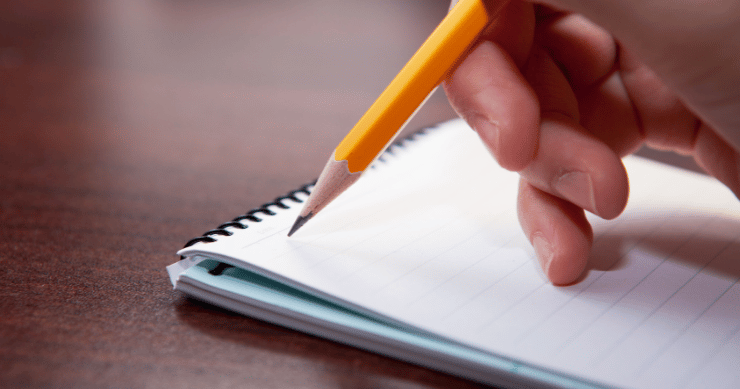災害で家が損壊したときに重要になるのが「罹災証明書」です。
罹災証明書は自治体が発行する公的な証明書で、保険金の請求や各種支援を受ける際に欠かせません。
この記事では、罹災証明書の基本的な役割から、発行の手順、保険金の請求方法までを解説します。
災害で家を失ったときこそ、着実に受け取れる支援を逃さずに活用してください。
目次
1.罹災証明書とは?
罹災証明書とは、災害による被害を公的に証明するために自治体が発行する書類のことです。
ここでは、罹災証明書の定義や発行する目的、罹災証明書と被災証明書の違いについて詳しく見ていきましょう。
災害対策基本法に基づく公的書類のこと
罹災証明書は、災害対策基本法に基づき、市区町村長が被災者の申請により発行することが定められた公的書類です。
地震や台風、火災などで住宅が損壊した際に、その被害の程度を市区町村が公式に認めるためのものです。
この証明書は、被害の程度が以下の区分で記載されています。
- 全壊
- 大規模半壊
- 半壊
- 一部損壊
- 災害ゴミ処分費用の減免 など
これにより、被災者がどの程度の被害を受けたのかが客観的に示され、被災者が受けられる支援や保険金請求の可否が客観的に判断できるのです。
罹災証明書は、被災地を管轄する市区町村役場の防災担当窓口で発行されます。
罹災証明書を取得できれば、保険金の請求だけでなく、税金の減免や各種支援制度の利用がスムーズになるでしょう。
罹災証明書を発行する目的
罹災証明書を発行する目的は、被災者が公的な支援や保険金を受ける際に、自らの被害状況を証明することです。
具体的に必要とされるケースは以下のとおりです。
- 生活再建支援金の申請
- 税金の減免
- 各種融資の申請
- 共済金の支払請求 など
支援制度は被害の程度に応じて支給額や対象が異なるため、罹災証明書が判断資料として用いられます。
例えば、義援金の支給額は被害区分によって数十万円から数百万円まで変動します。
こうした際に、被災者が着実に支援を受けられるようにするための「証拠」として役割を果たすのが罹災証明書なのです。
罹災証明書と被災証明書の違い
罹災証明書と似た名前の書類に「被災証明書」がありますが、目的と対象に違いがあります。
罹災証明書は住宅や家屋に限定して、調査員が現地で確認した結果をもとに発行し、被害の「程度」まで証明します。
保険金や税金の減免、生活再建支援金を受ける場合などが主な用途です。
一方、被災証明書は被災の届出があったという「被災した事実」だけを証明するものです。
住宅以外にも、車両や倉庫などの被災事実を証明する場合に使われます。
もし、被災直後で住宅の調査が間に合わない場合、まずは被災証明書を受け取り、あとから罹災証明書に切り替えるという対応も可能です。
2.罹災証明書の発行で受けられる主な支援
罹災証明書を発行すると、以下の公的支援を受けられます。
- 税金の減免
- 義援金・見舞金の支給
- 生活再建支援金の申請
- 公共料金・保険料の猶予
- 災害ゴミ処分費用の減免
それぞれ、詳しく解説します。
支援1.税金の減免
災害で住宅や家財に被害を受けた場合、罹災証明書を提出することで所得税や住民税の減免措置を受けられます。
税の軽減制度には「雑損控除」と「災害減免法」という2つの制度があり、どちらか有利なほうを選択できます。
【雑損控除】
損害額や災害関連の支出から保険金などを差し引いた金額を、所得から控除できる制度です。
控除額は以下の計算式で求められ、金額が大きいほうが適用されます。
- (損害額+災害関連支出−保険金等)−(総所得金額×10%)
- (災害関連支出−保険金等)−5万円
【災害減免法】
災害で住宅や家財が「時価に対して2分の1以上の損害」を受け、かつその年の合計所得金額が1,000万円以下の場合に適用となります。
所得に応じた軽減割合は次のとおりです。
- 所得金額が500万円以下→所得税額の全額免除
- 所得金額が500万円超~750万円以下→所得税額の1/2軽減
- 所得金額が750万円超~1,000万円以下→所得税額の1/4軽減
いずれの制度も、活用できれば数十万円単位で税負担を軽減できる可能性があります。
罹災証明書は、この減免手続きにおいて必須の書類です。
支援2.義援金・見舞金の支給
災害後には、自治体や日本赤十字社などから義援金や見舞金が支給される場合があります。
罹災証明書は、その支給を受ける際に必要となる証明書です。
支給額は被害内容、自治体、申請時期によって変動しますが、一世帯あたり20〜200万円程度が支払われた例もあります。
被害区分が「全壊」など高い被害認定を受けている場合、義援金支給額が高額になりやすいでしょう。
なお、義援金は被災者の生活再建を支援するために集められた寄付金であり、返済の必要はありません。
支援3.生活再建支援金の申請
全壊・半壊など一定の被害認定を受けると、被災者生活再建支援法に基づく「被災者生活再建支援金」の対象になります。
この支援金では、罹災証明書に記載された被害区分に応じて支給額が決まります。
支給は「基礎支援金」と「加算支援金」の2段階で構成されており、金額は以下のとおりです。
- 基礎支援金:50万円または100万円
- 加算支援金:50万円/100万円/200万円
(※単身世帯は上記金額の3/4相当)
さらに、令和2年12月の支援法の一部改正により、支援金の支給対象が中規模半壊世帯まで拡大となりました。(令和2年7月豪雨以降の災害が対象)
中規模半壊世帯の加算支援金は25万円・50万円・100万円です。
申請には罹災証明書が必須のため、正確な調査を受けてください。
支援4.公共料金・保険料の猶予
罹災証明書を提出することで、電気・ガス・水道・保険料などの支払い猶予措置を数か月間受けられる場合があります。
各市町村により「何か月分猶予されるか」「どの料金が対象か」が異なるため、申請先へ確認してください。
一般的には、災害発生から3〜6か月間の支払いが猶予の対象となります。
また、国民健康保険料や介護保険料についても、罹災の程度に応じて減免措置が設けられています。
なお、公共料金の猶予は自動的に適用される制度ではありません。
各事業者や自治体の窓口に罹災証明書を持参し、手続きを行いましょう。
支援5.災害ゴミ処分費用の減免
災害で発生した家具や家電、建材などの「災害ゴミ(災害廃棄物)」は、通常の家庭ゴミとは異なり、自治体が特別に回収・処理します。
多くの自治体では、罹災証明書や被災証明書を提示すると、処分手数料が無料または減額されます。
ただし、内容や手続きは自治体ごとに異なるため、必ずお住まいの市区町村に確認しましょう。
対象となるのは、壊れた家具や家電、畳、瓦礫、泥を含む家財などです。
申請時には、罹災証明書のほか、被害現場の写真を求められる場合があります。
搬入は自治体が指定する仮置き場や回収所へ行い、期間内であれば手数料が免除されるケースが一般的です。
環境省の「災害廃棄物対策指針」でも、廃棄物は衛生環境悪化を防ぐため速やかに処理すべきとされています。
罹災証明書を取得したら、各自治体の回収スケジュールと減免制度を確認し、早めに手続きを進めましょう。
3.火災保険・地震保険と罹災証明書の関係
保険金の請求において、罹災証明書の取り扱いは保険の種類によって異なります。
- 火災保険の場合
- 地震保険の場合
下記にて、それぞれの種類について見ていきましょう。
ケース1.火災保険の場合
火災保険の請求では、罹災証明書は必須ではありません。
保険会社が現地調査を行う場合は、証明書なしで支払いが進む場合もあります。
ただし、台風や大雨などの自然災害によって住宅が損壊した際には、被害証明として提出を求められるケースもあります。
提出できれば保険会社の審査が早く進む可能性もあるため、取得しておくと安心です。
なお、火災による被害の場合は、消防署による火災調査が完了してから罹災証明書の発行が受けられます。
そのため、調査への立ち会いを終えてから申請するようにしてください。
ケース2.地震保険の場合
地震保険の保険金請求にあたっても、罹災証明書の提出は原則不要となります。
地震保険は保険会社独自の調査によって被害認定を行うためです。
損害認定は「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4区分で行われ、罹災証明書における「全壊」「半壊」などの基準とは異なります。
保険会社の調査員が現地を訪問し、建物の傾きや損傷具合を専門的に確認して判定します。
ただし、罹災証明書は税金の減免や支援金の申請で役立つため、地震保険とは別に取得しておくと良いでしょう。
4.罹災証明書の被害区分と補償の関係
罹災証明書の被害区分によって、受けられる支援の内容は変わります。
- 全壊
- 大規模半壊・半壊
- 一部損壊
- 再調査の申請
4つの区分に分けて解説するので、それぞれ参考にしてください。
区分1.全壊
全壊とは、以下のように住み続けられない状態を指します。
- 損害割合が50%以上
- 住宅の主要な構造部分が大きく損傷している
- 居住スペースとしての機能を完全に失っている
全壊認定を受けると、生活再建支援金や義援金の対象となり、もっとも手厚い支援を受けられます。
支給額は、基礎支援金として100万円、住宅を建設・購入する場合の加算支援金が最大200万円です。
また、税金の減免や公営住宅への優先入居、各種融資の優遇措置なども適用の対象となります。
保険金の審査においても、全壊認定があれば手続きがスムーズに進むでしょう。
区分2.大規模半壊・半壊
大規模半壊と半壊は、住宅に損傷があるものの、修繕すれば住み続けられる状態を指します。
大規模半壊の基準は、以下のとおりです。
- 損害割合が40%以上50%未満
- 主要な構造部分に相当な損傷がある
- 大規模な修繕が必要
大規模半壊の場合、被災者生活再建支援金として基礎支援金が50万円、また加算支援金として最大200万円が支給されます。
一方、半壊の基準として以下が挙げられます。
- 損害割合が20%以上40%未満
- 一部の構造部分に損傷がある
- 修繕すれば居住可能
半壊の場合でも、令和2年以降の災害では中規模半壊として加算支援金が受けられるケースも見られます。
加えて、一部の補助金や再建支援金の対象となる場合があるため、保険金とあわせて活用できれば修繕費用の負担も軽減できるでしょう。
区分3.一部損壊
一部損壊は、以下のように住宅の一部に損傷があるものの、日常生活にはほとんど支障がない状態を指します。
- 損害割合が20%未満
- 軽微な損傷にとどまっている
- 小規模な修繕で対応可能
保険金の支払い対象にはなりますが、公的支援の対象外になるケースもしばしば見られます。
ただし、自治体によっては独自の支援制度を設けている場合もあるため、確認してみてください。
区分4.再調査の申請
認定結果に不服がある場合は、再調査を依頼できます。
例えば「実際の被害はもっと大きいのに、一部損壊と判定された」という場合などです。
再調査の申請期限は、多くの自治体で通知から30日以内と定められています。
申請時には、被害状況がわかる写真や修理見積書などの資料を添付すると、見直されやすくなります。
期限を過ぎると区分変更が難しくなるため、認定結果に疑問がある場合は早めに自治体窓口へ相談してください。
5.罹災証明書を発行するまでの流れ
ここからは、罹災証明書を発行するまでの流れを順番に確認していきましょう。
- 申請書を提出する
- 現地調査を受ける
- 被害の認定を受ける
- 罹災証明書の発行・受け取り
それぞれ参考にして、受け取り忘れのないようにしてください。
手順1.申請書を提出する
罹災証明書の申請は、被災地の市区町村役場で行います。
申請窓口は市区町村の防災担当課や市民課が基本となり、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)が必要です。
被害状況を示す写真を用意できていれば手続きもスムーズに進みます。
写真は、建物の外観、損傷箇所の詳細、複数の角度から撮影したものを用意してください。
大規模災害の場合、窓口が混雑しやすい状態になるため、郵送やオンライン申請に対応しているかを自治体のホームページで確認しておくと良いでしょう。
記入方法がわからない場合は窓口で相談できるため、直接訪問するのがおすすめです。
手順2.現地調査を受ける
次に、自治体の職員や委託調査員が現地を訪れ、住宅の被害状況を確認します。
調査は建築士などの専門職が担当し、以下の項目を中心に行われます。
- 屋根
- 外壁
- 基礎部分
- 室内の損傷
立ち会いは必須ではありませんが、被害の詳細を直接説明できるため可能な限り同席しましょう。
調査時間は通常1時間前後ですが、損傷が複雑な場合は長引くこともあります。
手順3.被害の認定を受ける
次に行われるのが、調査結果に基づいた被害区分の認定です。
被害区分は、損害割合によって以下のように分類されます。
- 損害割合50%以上:全壊
- 損害割合40%以上50%未満:大規模半壊
- 損害割合20%以上40%未満:半壊
- 損害割合20%未満:一部損壊
認定結果は、調査から数日〜1週間程度で通知されます。
ただし、大規模災害があり調査件数が多い場合は、さらに時間がかかることもあるでしょう。
なお、認定結果に納得がいかない場合は、再調査を申請できます。
より詳しい調査を希望する場合は、速やかに再調査の手続きを進めましょう。
手順4.罹災証明書の発行・受け取り
認定が完了すると、罹災証明書が交付されます。
認定後、1〜2週間ほどで罹災証明書の交付を受けられるのが一般的ですが、大規模災害時は1か月以上かかる場合もあります。
交付方法は自治体によって異なりますが、窓口での受け取り、郵送、オンライン交付などが一般的です。
窓口で受け取る場合は、本人確認書類と印鑑を持参してください。
罹災証明書は、保険金の請求や各種支援の申請で複数枚必要になるため、3〜5枚程度まとめて受け取っておくと安心です。
また、原本は保険会社や自治体に提出する場合があるため、コピーを取って保管しておくのがおすすめです。
6.保険金請求までの流れと罹災証明書の使い方
罹災証明書を使って保険金を請求するまでの流れは、以下のとおりです。
- 保険会社に連絡する
- 必要書類の提出
- 現地調査と審査
- 保険金の受け取り
それぞれ解説します。
手順1.保険会社に連絡する
まず、被害を確認したら早めに保険会社へ連絡してください。
多くの保険会社では、災害発生後すぐに専用の窓口を設置するため、電話またはWebサイトから手続きが可能です。
連絡する際には、以下を伝えます。
- 契約者の氏名
- 保険証券番号
- 被災した建物の住所
- 被害の概要
また、「必要書類の種類」や「現地調査の日程」などもあわせて確認しておくと安心です。
連絡が遅れると保険金の支払いまでに時間がかかるケースもあるため、被災後できるだけ早く連絡するのがベターです。
手順2.必要書類の提出
次に、罹災証明書・修理見積書・被害の写真などを揃えてください。
主な必要書類としては、以下のとおりです。
- 保険金請求書(保険会社から送付)
- 罹災証明書(自治体で発行)
- 修理見積書(施工業者が作成)
- 被害状況の写真(複数枚、できるだけ詳細に撮影)
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
修理見積書は、信頼できる業者に依頼して作成してもらいましょう。
書類が揃ったら、保険会社へ提出して審査を待ちます。
手順3.現地調査と審査
書類提出後には保険会社から調査員が派遣され、現地で被害状況を確認します。
調査では、屋根や外壁、室内の損傷など、保険金の支払い対象となる部分を詳しくチェックします。
立ち会いをする際には、被害の詳細を説明できるよう準備しておきましょう。
例えば「この損傷は今回の災害で発生したもの」といった説明ができると、スムーズに審査が進みます。
この審査には数日〜数週間かかるのが一般的です。
手順4.保険金の受け取り
審査完了後、契約内容に応じて保険金が支払われます。
支払い方法は、指定した銀行口座への振り込みが一般的です。
申請から支払いまでの目安は1〜2か月ほどですが、大規模災害ではさらに時間を要する場合もあるでしょう。
保険金を受け取ったら、修繕工事に着手できます。
工事完了後は、領収書や完了報告書を保管しておくと、追加手続きや確定申告の際に役立ちます。
7.罹災証明書を活用する際の注意点
罹災証明書を使ううえで気をつけたい点は、以下のとおりです。
- 提出期限を守る
- 再調査の申請期間を守る
- 複数の申請で提出を求められることがある
それぞれ参考にしてください。
注意点1.提出期限を守る
罹災証明書を使ったとしても、保険申請や支援申請には期限があるため、早めの準備を心がけてください。
期限を過ぎると、受けられる支援が無効になる場合があるため注意が必要です。
主な申請期限の目安は以下のとおりです。
- 火災保険の請求:損害発生から3年以内
- 被災者生活再建支援金の基礎支援金:災害発生日から13か月以内
- 加算支援金:災害発生日から37か月以内
不安な場合は罹災証明書を早めに取得し、各種申請の期限を一覧表にまとめて管理しましょう。
注意点2.再調査の申請期間を守る
罹災証明書を取得する際、再調査の申請期間を過ぎると区分変更が難しくなります。
多くの自治体では「認定結果の通知から30日以内」と定められているため、早めの確認が大切です。
「もう少し様子を見よう」と先延ばしにすると、気づいたときには期限を過ぎてしまいかねません。
認定結果を受け取ったらすぐに内容を確認し、疑問があれば速やかに申請しましょう。
窓口では、再調査の可否や必要書類について具体的な案内を受けられます。
注意点3.複数の申請で提出を求められることがある
複数の申請で同時に原本の提出を求められるケースがある点にも注意が必要です。
例として、以下の3つを同時に申請する場合には最低3枚が必要です。
- 火災保険の請求
- 税金の雑損控除
- 生活再建支援金の申請
罹災証明書の発行は無料のため、あらかじめ3〜5枚まとめて交付してもらうと安心です。
また、原本を提出する前には、必ずコピーを保管しておきましょう。
8.罹災証明書が必要になったらスムーズに手続きしましょう
災害で住宅が損壊したとき、罹災証明書の取得は生活を立て直すための最初の一歩です。
この証明書があれば、保険金の請求だけでなく、税金の減免、義援金や生活再建支援金の受給、公共料金の猶予など、さまざまな支援を受けられます。
Spread株式会社では、火災・水害・地震などによる家屋の復旧・修復サービスを提供しています。
災害後の清掃・除去・回復・修繕に関するお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。