親族が孤独死したと警察の連絡を受けたらどうすれば良い?葬儀までの流れを解説
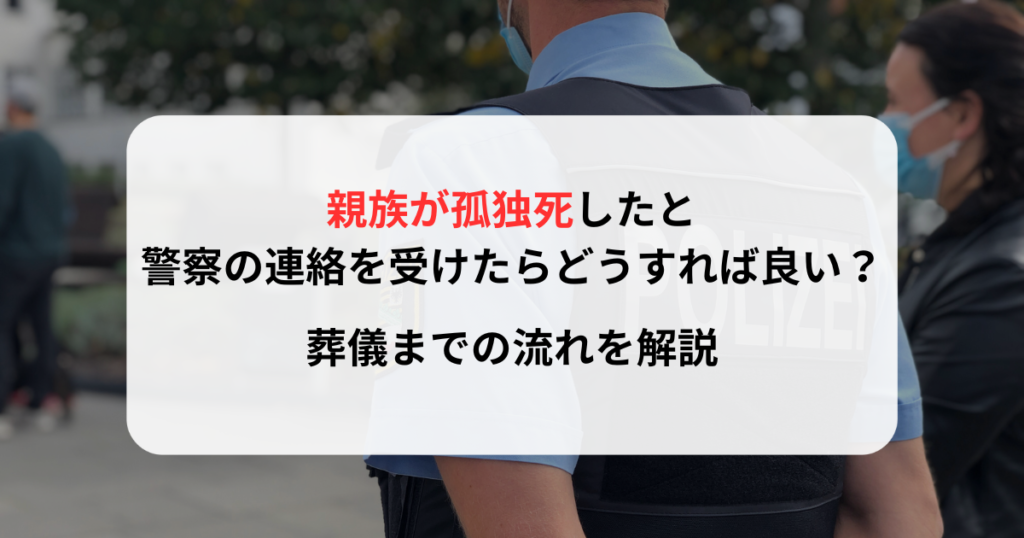
「警察から突然、親族の孤独死について連絡が…」
「遺体の引き取りに何を持っていけばいいの?」
「葬儀までの手続きはどうすればいい?」
以上のような不安な気持ちで、途方に暮れている方も多いのではないでしょうか。
警察からの連絡を受けてから葬儀までには、死亡届の提出や遺体の引き取り、特殊清掃の手配など、いくつもの重要な手続きが必要です。
この手続きを知らないまま対応すると、後々トラブルになったり、余計な費用がかかったりするケースも少なくありません。
本記事では、警察から孤独死の連絡を受けた際の流れと、必要な準備物、警察の具体的な対応について詳しく解説します。
ぜひ最後までご一読ください。
【突然の孤独死連絡】その後にやるべき10の対応、全部把握できていますか?
突然、親族の孤独死を知らされても、やるべき手続きは待ってくれません。
死亡届の提出、葬儀の準備、特殊清掃、家主との交渉、遺品整理、相続放棄の判断…
10を超える手続きと、高額な出費が、ご遺族の肩に一気にのしかかります。
当社では、特殊清掃・遺品整理など、現場対応に特化。
心の整理がつかない状況でも、私たちが「やるべきことの段取りと実行」を代行します。
見積もり無料・最短即日訪問。事態が深刻になる前に、まずはご相談ください。
専門技術 × 幅広い対応!特殊清掃・カビ除去・災害復旧・お片付け清掃もおまかせください!
目次
1.孤独死したと警察の連絡を受けてから葬儀までの流れ
親族が孤独死した場合、警察からの連絡を受けてからさまざまな手続きが必要になります。
以下の流れを把握して、1つずつ対応していきましょう。
- 警察からの連絡
- 死亡届を提出
- 葬儀の準備
- 葬儀と火葬を行う
- 特殊清掃業者を選定する
- 特殊清掃の実施
- 賃貸契約の清算
- 遺品の整理
- 相続について検討
- 死亡後の各種手続き
以下それぞれ簡単に流れを解説します。
流れ1.警察からの連絡
まず、警察からの連絡で親族の孤独死を知るケースが多いです。
警察は孤独死の通報を受けると、まず現場検証を行います。
この際、事件性の有無を確認するため、一時的に金品や貴重品を押収しますが、事件性がなければ返還されるので、ご安心ください。
現場検証中は、遺族であっても立ち入ることはできません。
警察は、現場で発見された公的書類や契約書などから遺族を特定し、親子や兄弟など血縁関係の近い順に連絡を取るのです。
身元確認が困難な場合はDNA鑑定なども実施され、検証の結果、事件性がないと判断された場合、死体検案書とともに遺体が遺族に引き渡されます。
流れ2.死亡届を提出
警察から死体検案書を受け取ったら、速やかに役所へ死亡届を提出しましょう。
提出期限は死亡を知った日から7日以内と法律で定められています。
もし警察が死体検案書を発行しない場合は、医師による死亡診断書が必要です。
死亡診断書がないと死亡届を提出できませんので、確実に入手しましょう。
流れ3.葬儀の準備
死亡届の提出後は、葬儀の準備です。
通常の葬儀と同様、まずは喪主を決定する必要があります。
ただし、孤独死の場合は遺族が喪主になることを躊躇するケースも少なくありません。
できるだけ早めに親族間で話し合い、葬儀の規模や形式を決定しましょう。
葬儀社への連絡や日程調整など、やるべきことを整理して進めていくことが重要です。
流れ4.葬儀と火葬を行う
葬儀の日程が決まったら、その地域の慣習やルールにしたがって葬儀・火葬を執り行いましょう。
孤独死の場合、遺体の状態によっては通夜を省略するなど、通常の葬儀とは異なる対応が必要になることもあります。
流れ5.相続の検討
葬儀と火葬を行った後は、相続について検討してください。
借金や滞納家賃、未払い税金などの負債がある場合、多くの遺族が相続放棄を選択します。
ただし、相続放棄は死亡を知った日から3か月以内に手続きしなければなりません。
また、遺産を少しでも受け取ったり処分したりすると、相続放棄ができなくなるので要注意です。
流れ6.特殊清掃業者を選定する
相続について検討しつつ、特殊清掃業者を選定しましょう。
孤独死が賃貸物件で発生した場合、原状回復は義務があるため必ず特殊清掃を行います。
遺体発見時には既に腐敗が進んでいることも多く、通常の清掃では対応できない場合がほとんどです。
信頼できる特殊清掃業者を選定するため、実績や料金体系、対応の丁寧さなどを確認しましょう。
複数の業者から見積もりを取ることをおすすめします。
専門技術 × 幅広い対応!特殊清掃・カビ除去・災害復旧・お片付け清掃もおまかせください!
流れ7.特殊清掃の実施
選定した業者による特殊清掃を実施します。
清掃完了前の立ち入りは危険を伴うため、業者の許可があるまでは絶対に入室しないでください。
また、保管したい遺品がある場合は、事前に業者と相談し、誤って処分されないよう明確に伝えておくことが重要です。
流れ8.賃貸契約の清算
賃貸物件の場合、契約の清算手続きが必要です。
家賃の滞納がある場合、原則として相続人に支払い義務が発生します。
ただし、保証会社や連帯保証人がいる場合は、契約内容を確認しましょう。
特殊清掃による原状回復が完了したら、物件を明け渡し、契約を終了してください。
流れ9.遺品の整理
孤独死現場の遺品は、原則として相続人が引き取ります。
しかし、多くの場合、遺品には死臭や体液が染み込んでおり、処分せざるを得ません。
汚染されていない遺品のみを選別して引き取り、相続人間で協議して決めましょう。
流れ10.死亡後の手続き
最後に、行政手続きを漏れなく行います。
住民票の世帯主変更・介護保険の資格喪失届・年金受給の停止・光熱費に関わるライフラインの停止などの手続きをしてください。
上記の手続きを放置すると後々トラブルになる可能性があるため、チェックリストを作成するなどして、確実に対応しましょう。
また、以下の記事では親族が孤独死した際にかかる費用についても解説しているので、合わせてチェックしてみてください。
孤独死の連絡が警察から来たら?かかる費用や手続きの流れを徹底解説
2.孤独死が起きて警察に行くときに必要な5つのもの
警察から孤独死の連絡を受けたら、すぐに警察署へ向かう必要があり、以下の5つのものを必ず用意しましょう。
- 身分証明書・印鑑
- 防寒着
- スマホの充電器
- 宿泊セット
- 遺体保管料などの費用
慌てて警察に向かうと必要なものを忘れやすいですが、遺体の引き取りから葬儀までスムーズに進めるために重要です。
(1)身分証明書・印鑑
遺体の引き取りには、引取人の身分証明書と実印が必須となります。
運転免許証やパスポートなど、顔写真付きの身分証明書を持参しましょう。
また、可能であれば故人の身分証明書も用意すると手続きがスムーズです。
印鑑は、必ずシャチハタではなく朱肉を使う実印を持参してください。
警察での手続きや死亡届の提出など、正式な書類に押印する機会が多くあります。
印鑑証明書がある場合は、併せて持参すると安心です。
証明書がないと、遺体の引き取りができない可能性もあるため、必ず確認してから出発しましょう。
(2)防寒着
警察署に行くのは普段着で問題ありませんが、遺体安置所での確認時には防寒着が必要不可欠です。
遺体安置所は遺体の腐敗を防ぐため、年間を通じて5度前後の低温に保たれています。
真夏でも室内は冷え切っているため、長袖のジャケットやカーディガンなどの防寒着を必ず持参しましょう。
また、警察署内も冷房が効いていることも多いため、防寒着があると快適に過ごせます。
(3)スマホの充電器
スマホの充電器も、必須アイテムです。
警察での手続き中、他の親族、葬儀社への連絡や相談相談、特殊清掃業者への見積もり依頼など、電話での連絡が頻繁に発生します。
また、インターネットで必要な情報を収集することも多いです。
手続きは長時間に及ぶことが多いため、充電器を忘れると途中で連絡が取れなくなる可能性も少なくありません。
(4)宿泊セット
現場が自宅から遠い場合や、手続きが長引く場合は、宿泊セットの持参を推奨します。
基本的な着替え一式に加え、洗面用具、下着類なども用意しましょう。
特に大切なのは喪服です。
遺体の引き取り後すぐに葬儀や火葬の手配が必要になる場合もあります。
通常、検死は当日中に終わりますが、その後の対応(葬儀社との打ち合わせ、特殊清掃の手配、遺品整理など)に数日かかることも珍しくありません。
慌てて自宅に戻る必要がないよう、3日分程度の着替えを用意しておくと安心です。
(5)遺体保管料などの費用
警察での手続きには、以下のような費用が必要となります。
現金での支払いが求められることが多いため、あらかじめ準備しておきましょう。
| 項目 | 費用 |
| 遺体保管料 | 2,000円(1泊あたり) |
| 検案料 | 約2万円~3万円 |
| 行政(承諾)解剖料 | 約8万円~12万円 |
| 死体検案書発行料 | 約5,000円~1万円 |
| 遺体搬送料 | 約1万2,000円~1万5,000円 |
この費用は地域や状況によって変動する可能性があります。
予備として、最大で20万円程度の現金を用意しておくと安心です。
クレジットカードが使える場合もありますが、確実を期すため現金での準備をおすすめします。
3.孤独死に対して警察が対応してくれる5つのこと
孤独死が発見された場合、警察は以下の5つの対応を順序立てて実施し、遺族が安心して故人との最期の別れを迎えられるよう支援します。
- 現場検証・家宅捜査で事件性の有無を確認
- 遺体の検視による身元確認と死因究明
- 必要に応じた遺体解剖の実施
- 死体検案書の発行手続き
- 遺体と貴重品の遺族への引き渡し
以下それぞれ解説します。
対応1.現場検証・家宅捜査
警察は孤独死が発見された現場で、まず身元特定と事件性の確認を行います。
遺体が発見された住宅では、その家の住民であることが多いものの、確実な身元確認が必要です。
警察は死亡した要因や経緯を詳しく調査し、万が一の事件性も考慮しながら捜査を進めます。
もし犯罪の可能性が少しでもある場合、証拠保全のため遺族や住宅の貸主であっても現場の立ち入りは禁止です。
部屋の鍵や貴重品も、事件性が完全に否定されるまでは警察署で保管されます。
対応2.遺体の検視
検視は、検察官や司法警察員によって実施される重要な調査です。
具体的には、医師からの意見聴取、発見者および親族の事情聴取、遺体の表面調査、指紋採取などが行われます。
警察に呼ばれた遺族は、この過程で事情聴取に協力しましょう。
第一発見者からも詳しい状況を聴取し、死亡時の状況を把握します。
通常、犯罪性がないと判断された場合、検視は半日から数日以内で完了です。
対応3.遺体解剖することも
警察は死因が不明確な場合や犯罪性が疑われる状況では、遺体の解剖を実施します。
解剖には主に2種類あり、事件性がないと判断された場合の行政解剖と、事件性を疑う場合の司法解剖です。
行政解剖は純粋に死因を特定するために行われ、司法解剖は犯罪捜査の一環として実施されます。
どちらの解剖が必要かは、それまでの捜査結果に基づいて警察が判断するものです。
遺族の心情に配慮しながらも、必要な場合は解剖が行われることをご理解ください。
対応4.死体検案書を発行
警察は検視終了後、死体検案書を発行します。
死体検案書は故人の氏名、死亡推定日時、死因などが記載され、医学的な死亡証明です。
通常の病院での死亡と異なり、孤独死の場合は警察による検視を経て、この死体検案書が発行されます。
この書類は火葬許可証の発行や相続手続きに必要不可欠です。
死体検案書は役所提出後、原本は返却されないため、必ずコピーを保管しておきましょう。
また、相続手続きなど、今後のさまざまな手続きでも必要となるため、大切に保管することが重要です。
対応5.遺体の引き渡し
警察による現場検証・検視が完了し、死因や死亡推定日時が確定し、遺族による身元確認が終わった後が遺体の引き渡しタイミングです。
同時に、警察署で保管されていた貴重品や部屋の鍵なども返還されます。
この時点で、葬儀や特殊清掃、遺品整理などの手続きを進めることが可能です。
スムーズな対応のために、警察が遺体を保管している間に、葬儀社や特殊清掃業者の選定など、可能な準備を進めておくことをおすすめします。
遺体の引き渡し後は、故人との最期の別れに向けた準備に専念しましょう。
4.孤独死後に起こりやすいトラブルとその回避方法
最後に、孤独死が発生したあとに起きがちなトラブルとその対策について紹介します。
孤独死の後には、費用負担の誤解や親族間の意見対立、悪質業者による高額請求など、遺族が直面しやすいトラブルが発生しがちです。
この内容を知らなければ、思わぬ高額請求を受けたり、親族間の関係が悪化したり、解決に時間と労力を浪費するリスクがあります。
1つずつ、見ていきましょう。
トラブル1.費用負担に関する誤解
孤独死にかかる費用を誰が負担するのかを明確にしておくことで、後からの誤解や請求トラブルを避けやすいです。
遺体搬送・検案料・葬儀費用・特殊清掃などは、状況により負担者が異なります。
相続人や連帯保証人が費用請求を受けるケースが多く、認識に差があるとトラブルになりやすいです。
実際に、兄弟間で「葬儀費用は全員で分担すると思っていたが、自分だけに請求が来た」と揉めた事例があります。
相続放棄をすれば費用負担を免れる一方、遺産も一切受け取れなくなるため、判断が重要です。
請求の範囲と相続の関係を理解し、早めに弁護士や行政に確認することで、費用負担に関する誤解を防げます。
トラブル2.親族間での揉め事
孤独死後の対応では、親族間での意思疎通を徹底することがトラブル防止につながります。
葬儀の形式や費用分担、遺骨や遺品の扱いは感情が絡みやすく、事前に合意が取れていないと対立が起きやすいからです。
例えば、遺骨を誰が引き取るかを巡って「自分が保管するべきだ」と主張が対立し、家庭裁判所に持ち込まれたケースもあります。
費用面でも「自分は負担したくない」と不公平感が生まれると関係が悪化するでしょう。
重要な判断は複数人で共有し、書面やメッセージで記録を残すことで、後からの言い分の食い違いを防げます。
トラブル3.業者間との揉め事
特殊清掃や葬儀の業者は、複数社を比較し信頼できる会社を選ぶことが重要です。
悪質な業者に依頼すると高額請求や作業の不備が発生し、再度依頼が必要になって余計な費用と時間がかかります。
「基本料金5万円」と安く提示して契約させ、作業後に消臭・害虫駆除費用を別途請求し、最終的に30万円以上になった例も耳にすることが多いです。
業者との契約前に見積もりの内訳や追加費用の有無を確認し、口コミや実績を調べましょう。
そうすることで、業者選びの失敗を防ぎやすくなります。
5.親族が孤独死したと連絡が来たら慌てず対応しよう
親族の孤独死という突然の知らせに、多くの方が混乱し途方に暮れますが、警察からの連絡を受けてから葬儀までの対応は、基本的な流れに沿って進められます。
まず大切なのは、警察に訪問する時に必要な持ち物を準備することです。
身分証明書や印鑑といった基本的なものから、場合によっては宿泊が必要となる可能性も考慮し、防寒着や充電器なども用意しましょう。
また、遺体保管料などの費用も必要となるため、ある程度の現金も持参することをおすすめします。
相続の検討や死亡後の各種手続きなど、時間をかけて進める必要がある事項も少なくありません。
突然の出来事で心理的な負担も大きいと思いますが、特殊清掃が必要な場合は、私たちSpread株式会社にぜひご相談ください。
専門知識と豊富な経験をもとに、現場の状況に応じた適切な対応をご提案いたします。
ご遺族の心身の負担を少しでも軽くできるよう、誠実にサポートいたします。
専門技術 × 幅広い対応!特殊清掃・カビ除去・災害復旧・お片付け清掃もおまかせください!







