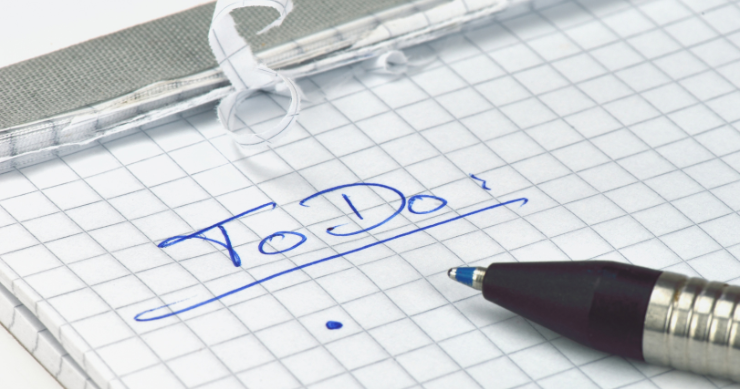火事は私たちの生活を一変させる大きな災害です。
住まいや大切な持ち物を失うだけでなく、その後の生活再建に向けてさまざまな手続きが必要になります。
しかし、被災直後は何から始めれば良いのか、どのような支援が受けられるのかなど、不安や戸惑いでいっぱいになってしまうことも珍しくありません。
そこでこの記事では、火事になったあとに必要な手続きを優先度や時系列に沿って詳しく解説します。
この記事を参考に、なるべく落ち着いて手続きを進めていきましょう。
【火災後すぐにやるべきこと】順番を間違えると損をするかもしれません
火災後、気が動転している中でも、手続きや連絡は待ってくれません。
やるべきことを忘れてしまうと、保険金が下りなかったり、公的支援を受けられないことも。
当社では、罹災証明用の記録サポートから清掃・廃棄物処分・業者間連携まで一括対応。
見積もり無料・最短即日対応・秘密厳守。
知らずに損をする前に、まずはご相談ください。
専門技術 × 幅広い対応!特殊清掃・カビ除去・災害復旧・お片付け清掃もおまかせください!
1.火事になったら最初に必要になる手続き
火事になったら最初に必要になる手続きは、次の5つです。
- 火災調査への立ち会い
- 罹災証明書の取得
- 保険会社への連絡
- ライフラインの停止
- 解体工事の依頼
それぞれ解説します。
手続き1.火災調査への立ち会い
火災発生後、消防署と警察署による火災調査が実施されます。
この調査は、出火原因の特定や延焼状況の確認を目的としており、建物の所有者や居住者には立ち会いが求められます。
調査官から火災発生時の状況や建物の使用状況について質問を受けるため、できるだけ正確に答えるようにしましょう。
この調査結果は、後の罹災証明書の発行、ひいては保険金請求の際の重要な資料です。
調査の日程調整は消防署から連絡がありますが、早期の実施が望ましいため、積極的に消防署とコミュニケーションを取ることをおすすめします。
手続き2.罹災証明書の取得
罹災証明書は、火災による被害の程度を公的に証明するもので、市区町村役場の防災担当窓口で申請・取得できます。
申請には、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)と、被害状況を示す写真があると手続きもスムーズです。
この証明書は、火災保険の請求や各種支援制度の利用、税金の減免申請などに必須のものです。
消防署による火災調査を完了していることが発行の条件となるため、調査への立ち会いを終えてから申請するようにしましょう。
被害の程度によって証明書の内容が異なるため、正確な被害状況の確認が重要です。
手続き3.保険会社への連絡
火災保険や家財保険に加入している場合、できるだけ早く保険会社に連絡することが重要です。
多くの保険会社では24時間対応のコールセンターを設置していますので、火災発生後速やかに連絡を入れましょう。
保険金請求に必要な書類(罹災証明書、被害状況の写真、修理見積書など)の準備を始めます。
保険会社の担当者から具体的な請求手続きの説明を受け、必要書類を確認しましょう。
また、火災保険の補償内容や請求可能な項目について詳しく確認することで、適切な保険金請求が可能になります。
手続き4.ライフラインの停止
火災発生後は、二次被害を防ぐため、水道・電気・ガスなどのライフラインを速やかに停止してください。
各供給会社に連絡し、安全確認が完了するまでは使用を控えましょう。
特に電気やガスは、配線や配管の損傷により危険な状態になっている可能性があります。
専門家による点検を受けるまでは、たとえ使用可能に見えても決して使用しないでください。
水道に関しても、消火活動による水損で建物の構造に影響が出ている可能性があるため、安全確認が必要です。
手続き5.解体工事の依頼
火災により建物が使用不可となった場合、解体工事が必要になります。
解体工事の前に、建物内から可能な範囲で物品を回収することも重要です。
多くの自治体では、火災による解体工事に対して「一般廃棄物処理費用減免制度」などの支援制度を設けています。
事前に役所へ相談し、利用可能な制度を確認しましょう。
なお、解体工事の着手前に必要な許可申請や届出についても確認が必要です。
また、以下の記事では火災ゴミの片付け手順について解説しています。
自力での対応方法から業者への依頼のポイントまで、具体的な手順も紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。
火災ごみを片づける手順は?費用の目安や必要なものについて解説
専門技術 × 幅広い対応!特殊清掃・カビ除去・災害復旧・お片付け清掃もおまかせください!
2.火事になったら次に必要になる手続き
火事になったら次に必要になる手続きには、以下が挙げられます。
- 住民票の写しの発行
- 運転免許証の再交付
- マイナンバーカードの再交付
- 実印や印鑑登録証の再作成
- 預金通帳やキャッシュカードの再発行
- クレジットカードの再発行
- 健康保険証の再発行
- 基礎年金番号通知書の発行
- 保険証券の再発行
- 燃えた現金の引き換え
それぞれの手続きは、生活を立て直す上で重要なものばかりです。
できるだけ早めに手続きを進めることを推奨します。
手続き1.住民票の写しの発行
火災で身分証明書をすべて消失してしまった場合、まずは住民票の写しを取得することが重要です。
住民票の写しは、その後のさまざまな手続きで身分証明書として使用できるためです。
市区町村の窓口で申請が可能で、本人確認ができれば即日発行してもらえます。
火災で身分証明書をすべて失った場合でも、本人であることを確認できる書類(健康保険証や年金手帳など)があれば申請できます。
それらの書類もすべて消失してしまった場合は、窓口で事情を説明し、本人確認の方法について相談してください。
住民票の写しは、運転免許証やマイナンバーカードなど、他の身分証明書の再発行手続きにも必要となるため、優先的に取得しましょう。
手続き2.運転免許証の再交付
運転免許証を消失した場合は、警察署や運転免許センターで再交付の手続きを行います。
申請には、本人確認書類として住民票の写しや、顔写真付きの身分証明書が必要です。
再交付の申請には、本人が直接窓口に出向く必要があります。
申請時に必要な書類は、本人確認書類(住民票の写し、パスポートなど)、写真1枚(縦3cm×横2.4cm)、手数料です。
手数料は地域によって異なりますが、3,000円程度が一般的です。
即日発行が可能な場所もありますが、地域によっては後日郵送となる場合もあります。
転免許証は身分証明書としても重要なため、できるだけ早めに再交付を受けることをおすすめします。
手続き3.マイナンバーカードの再交付
マイナンバーカードを消失した場合は、まず紛失届を出す必要があります。
24時間365日対応のマイナンバー総合フリーダイヤルでは電話での届出が可能で、その後はお住まいの市区町村の窓口で再交付申請を行います。
申請には本人確認書類(住民票の写しなど)と、再交付手数料が必要です。
また、電子証明書も併せて再発行する場合は、別途手数料が必要になります。
マイナンバーカードはさまざまな行政手続きに必要となるため、消失した場合は速やかに再交付の手続きを進めることが重要です。
なお、再発行には1〜2か月程度かかることが一般的です。
再交付されるまでの間は、マイナンバー通知カードと身分証明書の組み合わせで代用できます。
手続き4.実印や印鑑登録証の再作成
実印や印鑑登録証を消失した場合は、お住まいの市区町村の窓口で再作成を行ってください。
まず新しい実印を作成し、次に市区町村の窓口で以前の印鑑登録の抹消手続きを行います。
その後、新しい実印で印鑑登録の申請を行うことで手続きが完了します。
申請時には本人確認書類(住民票の写しなど)と手数料が必要です。
印鑑登録証明書は、不動産取引や各種契約時に必要となる重要な書類のため、できるだけ早めに再登録することをおすすめします。
手続き5.預金通帳やキャッシュカードの再発行
預金通帳やキャッシュカードを消失した場合は、まず取引のある銀行に連絡し、キャッシュカードの利用停止手続きを行う必要があります。
再発行の手続きは銀行窓口で行えることが一般的です。
多くの場合、本人確認書類(運転免許証や住民票の写しなど)が必要になります。
通帳、キャッシュカード、登録印のすべてを消失した場合は、その旨を窓口で説明し、必要な手続きについて相談してください。
再発行には手数料がかかる場合があるため、手続き前に確認しておくと安心です。
新しいカードが手もとに届くまでには1〜2週間程度かかることが一般的です。
この間の現金引き出しについては、窓口での払い戻し手続きで対応可能です。
手続き6.クレジットカードの再発行
火災でクレジットカードを紛失・焼失した場合は、すぐにカード会社に連絡する必要があります。
第三者による不正利用を防ぐため、カードの利用停止手続きを行いましょう。
再発行の申請には、本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)が必要です。
本人確認書類も焼失している場合は、その旨をカード会社に伝え、相談しましょう。
通常、再発行には1〜2週間程度かかり、手数料が発生する場合もあるため、カード会社に確認してください。
手続き7.健康保険証の再発行
健康保険証を焼失した場合、加入している保険の種類によって手続き先が異なります。
会社員の方は勤務先の人事部門に相談し、国民健康保険に加入している方は市区町村の窓口で再発行の手続きを行ってください。
申請時には本人確認書類が必要ですが、火災で焼失している場合は、罹災証明書を提示することで対応してもらえる場合もあります。
再発行までの間に医療機関を受診する必要がある場合は、加入している保険者に相談すれば「健康保険被保険者資格証明書」を発行してもらえるため確認してみてください。
通常、再発行手数料は無料で、1週間程度で新しい保険証が手もとに届きます。
手続き8.基礎年金番号通知書の発行
基礎年金番号通知書を焼失した場合は、お近くの年金事務所で再発行の手続きができます。
この書類は年金の手続きや確認の際に必要となる重要な書類です。
再発行申請には本人確認書類が必要ですが、火災で焼失している場合は罹災証明書で代用できる場合があります。
年金事務所での手続きの際は、基礎年金番号が分かると手続きもスムーズです。
番号が不明な場合でも、氏名、生年月日、住所などの情報から照会が可能です。
再発行は無料で、通常1週間程度で新しい通知書が郵送されます。
なお、年金の受給者の方は、年金証書の再発行も忘れずに申請しましょう。
手続き9.保険証券の再発行
火災で保険証券を焼失した場合は、加入している保険会社に連絡して再発行を依頼します。
生命保険、損害保険、医療保険など、加入しているすべての保険について確認が必要です。
保険会社への連絡の際は、契約者名、生年月日、住所などの基本情報に加え、可能であれば証券番号も伝えましょう。
保険証券の再発行は基本的に無料です。
本人確認書類が必要ですが、火災で焼失している場合は、罹災証明書での代用が可能な場合があります。
なお、保険証券の再発行までには1〜2週間程度かかるのが一般的です。
手続き10.燃えた現金の引き換え
火災で現金が焼損した場合、日本銀行や一般の金融機関で新しい紙幣や硬貨と交換できます。
ただし、交換可能かどうかは損傷の程度によって判断されます。
紙幣の場合、表面積の3分の2以上が残っていれば全額、2分の1以上3分の2未満であれば半額で引き換えが可能です。
引き換えの際は、焼損したお金を丁寧に集めて封筒やビニール袋に入れ、できるだけ原形を保ったまま持参しましょう。
硬貨の場合も、変形や損傷の程度によって引き換えの可否が決まります。
なお、完全に灰になってしまった場合や、表面積の2分の1未満しか残っていない場合は、残念ながら引き換えができません。
3.火事になったら受けられる支援の手続き
火災で被災された方には、さまざまな支援制度や減免措置が用意されています。
以下の手続きを行うことで、住まいの確保から生活再建までの支援を受けることができます。
- 市営住宅への一時入居
- 見舞金や援護物資の支給
- 生活福祉資金の貸付
- 一般廃棄物処理費用減免制度
- 災害減免法
- 雑損控除
- 国民健康保険料の減免
- 国民年金保険料の免除
- 住民税の減免
- 火災ごみ処理手数料の減免
それぞれ解説します。
手続き1.市営住宅への一時入居
火災で自宅が焼失したり大きな被害を受けたりして住める状態でない場合、市町村が管理する公営住宅に一時的に入居できる制度があります。
入居期間は通常6か月以内で、家賃は通常の市営住宅より低く設定されています。
申し込みは市区町村の住宅課で受け付けており、罹災証明書の提出が必要です。
入居の審査は比較的早く行われ、緊急性が高い場合は数日程度で入居できることもあります。
ただし、空室状況によっては希望する地域の住宅に入居できない場合もあるため、できるだけ早めに相談することをおすすめします。
手続き2.見舞金や援護物資の支給
火災の被害に遭われた方に対して、自治体や社会福祉協議会から見舞金や援護物資が支給される制度があります。
見舞金の額は自治体によって異なりますが、数万円程度が支給されるケースが一般的です。
援護物資としては、毛布や日用品、食料品などの生活必需品が提供されます。
申請には罹災証明書が必要で、市区町村の福祉課や社会福祉協議会の窓口で手続きを行います。
支給までの期間は通常1週間程度ですが、自治体によっても異なるため詳細は窓口で確認しましょう。
手続き3.生活福祉資金の貸付
火災で被災し、生活の立て直しが必要な低所得世帯を対象に、社会福祉協議会が無利子または低利子で資金を貸し付ける制度があります。
貸付限度額は原則として150万円以内で、返済期間は最長10年です。
資金の使い道は住宅の補修費用や家財の購入費用などが対象で、世帯の収入状況や被害状況に応じて貸付条件が決定されます。
申請には罹災証明書のほか、世帯の収入を証明する書類などが必要です。
審査には通常2週間から1か月程度かかりますが、緊急性が高い場合は審査期間が短縮されることもあります。
手続き4.一般廃棄物処理費用減免制度
火災で発生した廃棄物(焼けた家具・家財など)の処理費用を減免する制度があります。
通常、大量の廃棄物を処理する場合は有料となりますが、この制度を利用することで費用が免除または軽減されます。
申請は自治体の環境課または清掃事務所で受け付けており、罹災証明書の提出が必要です。
減免の対象となる廃棄物の種類や量には制限があるため、事前に確認が必要です。
また、処理方法や搬出方法についても指示があるため、必ず窓口に相談してから作業を始めるようにしましょう。
手続き5.災害減免法
災害減免法は、火災により住宅や家財に被害を受けた場合、所得税や住民税が減免される制度です。
被害金額が住宅や家財の価額の2分の1以上で、被害を受けた年の所得金額が1,000万円以下の場合に適用されます。
手続きをする場合は確定申告時に税務署で災害減免法適用申請を行う必要があり、罹災証明書のほか、被害状況を証明する写真や修繕費用の見積書などの提出が必要です。
減免額は被害の程度と所得金額によって決定され、最大で税額の全額が免除されることもあります。
なお、申請期限は災害があった日から2年以内です。
手続き6.雑損控除
火災によって住宅や家財に損害を受けた場合、確定申告を通じて所得税の軽減を受けられる制度が「雑損控除」です。
この控除を受けるためには、確定申告時に必要書類を提出する必要があります。
申請に必要な書類は、罹災証明書、修繕費用の領収書、損害額を証明する書類などです。
控除額は、損害額から保険金などで補填された金額を差し引いた実質的な損失額にもとづいて計算されます。
雑損控除は、災害があった年の所得から控除する方法と、前年の所得から控除する方法を選択できます。
どちらが有利か検討の上、申告しましょう。
なお、申告の際は税務署に相談することで、より詳しい説明を受けられます。
手続き7.国民健康保険料の減免
火災により経済的な打撃を受けた場合、国民健康保険料の減免制度を利用できる可能性があります。
減免を受けるためには、お住まいの市区町村役場の国民健康保険課への申請が必要です。
減免の対象となる条件は、火災による住宅の損害の程度や、世帯の収入状況などによって判断されます。
申請には、罹災証明書や収入状況を証明する書類などが必要です。
減免の割合は自治体によって異なりますので、確認してみてください。
また、減免期間は通常、災害が発生した月から一定期間とされています。
早めに窓口に相談し、必要な手続きを進めることをおすすめします。
手続き8.国民年金保険料の免除
火災により収入が減少した場合、国民年金保険料の免除制度を利用できます。
申請は日本年金機構の年金事務所または市区町村役場の国民年金窓口で受け付けています。
免除申請には、罹災証明書のほか、収入状況を証明する書類が必要です。
審査の結果、全額免除や一部免除が認められる場合があります。
免除期間中も年金受給資格期間にカウントされるため、将来の年金受給に影響はありません。
ただし、全額免除の場合、将来受け取る年金額は保険料を納付した場合の2分の1となります。
後日、経済状況が改善した際には、免除期間の保険料を遡って納付(追納)することも可能ですが、追納する場合は免除された期間から10年以内に行う必要があります。
手続き9.住民税の減免
火災により住宅や家財に損害を受けた場合、住民税(市町村民税・都道府県民税)の減免を受けられる制度があります。
減免を受けるためには、市区町村役場の税務課への申請が必要です。
減免の対象になるかは、火災による損害の程度や世帯の収入状況などによって判断されます。
一般的に、住宅や家財の損害割合が30%以上の場合に対象となることが多いですが、具体的な基準は自治体によって異なります。
申請には、罹災証明書や損害額を証明する書類、収入状況を証明する書類などが必要です。
減免額は損害の程度に応じて決定され、場合によっては全額免除となることもあります。
申請期限が設けられていることも多いため、早めに窓口で相談することをおすすめします。
手続き10.火災ごみ処理手数料の減免
多くの自治体では火災により発生したごみの処理手数料を減免する制度を設けています。
減免を受けるためには、自治体の環境課や清掃事務所への申請が必要です。
申請時には罹災証明書の提示が求められるほか、減免制度を利用する場合は、事前に自治体の指定する方法で分別を行い、指定された搬入場所に持ち込む必要があります。
なお、自治体によっては処理できるごみの種類や量に制限を設けていることも少なくありません。
また、搬入時期や搬入方法についても規定があるため、必ず事前に窓口で確認しましょう。
処理を業者に依頼する場合は、減免制度の対象となるか確認することをおすすめします。
4.火事になったら早めに手続きを済ませましょう
火事の発生後は、さまざまな手続きが必要になります。
本記事で解説してきた通り、まずは以下の手続きから進めていきましょう。
- 火災調査への立ち会い
- 罹災証明書の取得
- 保険会社への連絡
- ライフラインの停止
- 解体工事の依頼
不安なことがあれば、自治体の窓口や保険会社に相談し、必要な支援を受けながら、手続きを進めてください。
こうした手続きと並行して、焦げ跡やスス汚れ、消火剤による汚染といった現場の清掃も必要です。
私たちSpread株式会社では、火災後の清掃や消臭、現場復旧作業を専門に行っています。
ぜひお気軽にご相談ください。
専門技術 × 幅広い対応!特殊清掃・カビ除去・災害復旧・お片付け清掃もおまかせください!
また、私たちSpread株式会社のコラムにある「火災復旧」に関する情報をまとめたものが以下の記事です。
火災後の清掃・修繕・有害物質除去・費用相場など、幅広い内容を紹介しています。
他にも火災復旧に関する疑問や悩みがあれば、こちらの記事をチェックしてみてください。