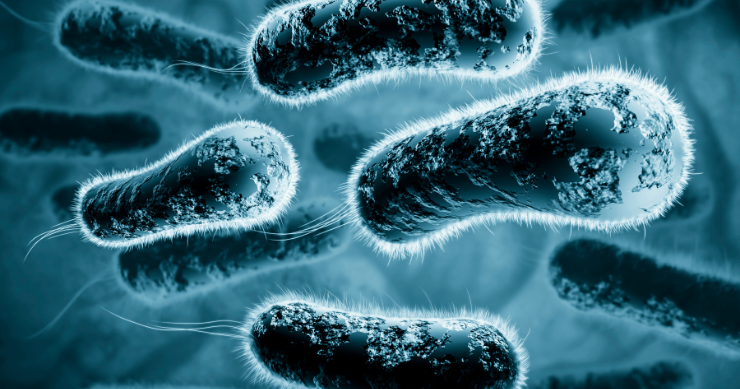レジオネラ属菌による感染症は、適切な対策を行わないと急激に重症となり死亡する場合もあるがあります。
中でも温浴施設や給湯設備を管理する立場にある方にとって、レジオネラ対策は避けて通れない重要な課題です。
公衆浴場や温泉施設、ホテルなどで、レジオネラ感染症の集団発生はたびたび報告されています。
この事例の多くは、適切な衛生管理が行われていなかったことが原因です。
そこでこの記事では、レジオネラ属菌の基本的な知識から、感染症の種類、感染原因、そして具体的な対策方法まで詳しく解説します。
対策は難しく感じるかもしれませんが、正しい知識と定期的なメンテナンスで十分に予防できるものです。
この記事を参考に、効果的な対策を実施していきましょう。
目次
1.レジオネラ属菌とは?
レジオネラ属菌とは、自然界の水環境に広く生息する細菌の一種です。
人工的な水設備で繁殖しやすい特徴を持っており、温度が20〜50℃の環境でもっとも活発に増殖します。
20〜50℃の環境は、多くの温浴施設や給湯設備の温度と重なるため、注意が必要です。
主にレジオネラ属菌は単独で増殖できず、水を使用する設備に付着するぬめり(生物膜:バイオフィルム)に生息するアメーバなどの微生物に寄生して増殖します。
そして、エアロゾル(細かい水滴)として空気中に舞い上がり、人が吸い込むことで感染を引き起こします。
2.レジオネラ属菌による感染症
レジオネラ属菌による感染症には、主に以下の2種類があります。
- レジオネラ肺炎
- ポンティアック熱
この感染症は同じ菌によって引き起こされますが、症状の重さや経過が異なります。
それぞれの感染症について、以下で詳しく見ていきましょう。
感染症1.レジオネラ肺炎
レジオネラ肺炎は、レジオネラ属菌による感染症の中でも、急激に重症となり死亡する場合もあることで注意が必要な疾患です。
一般的な肺炎と症状が似ていますが、通常の抗生物質が効きにくいという特徴を持ちます。
主な感染経路はエアロゾル(温泉の湯気やシャワーの霧)を吸い込むことです。
発症すると以下の症状が現れます。
- 高熱、呼吸困難
- 筋肉痛、吐き気
- 下痢、意識障害 など
症状が進行すると、呼吸困難が悪化し、入院治療が必要になることもあります。
特に高齢者や喫煙者、基礎疾患や慢性疾患(糖尿病、心臓病など)を持つ方、免疫力が低下している方は重症化しやすいため、早期の医療機関受診が重要です。
感染症2.ポンティアック熱
ポンティアック熱は、レジオネラ肺炎と比べて軽症の感染症です。
インフルエンザや風邪に似た症状が特徴で、通常は2〜5日程度で自然に回復します。
レジオネラ肺炎と同様にレジオネラ菌を含むエアロゾルを吸い込むことで発症します。
主な症状としては以下の通りです。
- ・発熱
- ・寒気(悪寒)
- ・筋肉痛 など
肺炎の症状は見られず、咳や呼吸困難はあまり現れません。
ポンティアック熱は健康な人でも発症する可能性があり、集団発生することもあります。
症状は軽いものの、数日間の体調不良を引き起こすため、施設管理者は予防対策を徹底する必要があります。
3.レジオネラ属菌に感染する原因
レジオネラ属菌に感染する主な原因として、以下の6つが挙げられます。
- 貯湯槽
- ろ過器
- 循環配管
- 気泡発生装置・ジェット噴射装置・打たせ湯
- シャワー
- 露天風呂
いずれも、レジオネラ属菌が繁殖しやすい環境を作り出す要因です。
それでは、それぞれの原因について詳しく見ていきましょう。
原因1.貯湯槽
レジオネラ属菌に感染する原因の1つ目は、温水を貯めておく設備である貯湯槽です。
貯湯槽は40°C前後の温水が長時間滞留する環境で、レジオネラ菌の増殖に最適な環境です。
貯湯槽の底部には、スケール(水垢)やスライム(粘液状の物質)が溜まりやすく、レジオネラ菌の住処となります。
そのため、常に60℃以上に保つことと、清掃が必要です。
また貯湯槽内の温度が不均一になると、部分的に菌が繁殖する「温度ムラ」が生じることもあります。
定期的な点検と適切な温度管理が重要です。
原因2.ろ過器
レジオネラ属菌に感染する原因の2つ目は、ろ過器です。
ろ過器は浴槽水をきれいにする役割を持つ設備ですが、水の循環によりろ過器内には有機物や微生物が溜まりやすく、レジオネラ菌が増殖する環境となります。
中でも、ろ過材(砂やカートリッジなど)に菌が定着しやすい傾向です。
ろ過材の交換や殺菌処理を1週間に1回以上に行う必要があり、砂ろ過器の場合は逆洗浄だけでは不十分で、定期的な砂の交換や消毒も必要です。
加えて、ろ過器の周辺配管にもバイオフィルムが形成されやすいため、配管も含めた洗浄・消毒も求められます。
原因3.循環配管
レジオネラ属菌に感染する原因の3つ目は、浴槽水を循環させる循環配管です。
配管内部にバイオフィルム(細菌の膜)が形成されると、レジオネラ菌が増殖してしまいます。
バイオフィルムは通常の塩素消毒では完全に除去できないため、特別な対策が必要です。
特に配管の曲がり部分や分岐点、使用頻度の低い配管などは水の流れが滞りやすく、バイオフィルムが形成されやすい場所です。
そのため、高温洗浄や薬剤洗浄での対策が求められます。
1年に1回程度で配管洗浄を行わないと、いくら浴槽を清掃しても、配管から常に菌が供給される状態になってしまいます。
原因4.気泡発生装置・ジェット噴射装置・打たせ湯
レジオネラ属菌に感染する原因の4つ目は、気泡発生装置・ジェット噴射装置・打たせ湯です。
いずれの設備も、水流によりエアロゾルが発生しやすく、吸い込むことで感染のリスクが高まります。
特に気泡浴槽(ジャグジーなど)は、大量のエアロゾルを発生させます。
装置内部には水垢や汚れが溜まりやすく、使用頻度が低い場合は内部の水の滞留を引き起こし菌も増殖しやすくなるのです。
この場合、使用後の洗浄と消毒を徹底することが重要です。
特に営業終了後は、装置内部の水を完全に排出し、乾燥させることが望ましいでしょう。
原因5.シャワー
レジオネラ属菌に感染する原因の5つ目は、シャワーです。
シャワーは日常的に使用する設備ですが、シャワーヘッドの内部に菌が溜まりやすく、使用時にエアロゾルとして放出されるからです。
長期間使用していないシャワーは内部の水が滞留して菌を増殖しやすいため、定期的に熱湯消毒や除菌剤で洗浄する必要があります。
細かい穴においても、カルシウムなどのスケールが付着しやすく、その上にバイオフィルムが形成されます。
そのため、連日使用している循環させた浴槽水はシャワーに使用しないようにしましょう。
また、シャワーヘッドとホースは半年に1回以上点検し、内部の汚れとスケールは1年に1回以上洗浄と消毒することが推奨されています。
原因6.露天風呂
レジオネラ属菌に感染する原因の6つ目は、露天風呂です。
屋外にあるため、外部の細菌や藻類が入り込みやすいのです。
例えば、風で運ばれる土や落ち葉、虫なども入り込み、有機物が増えることでレジオネラ菌の栄養源となります。
日光が当たる露天風呂では藻類が繁殖しやすいほか、雨水の流入も菌の増殖を促進する要因になります。
そのため、露天風呂の浴槽湯が配管を通じて内湯に混じらないようにする構造設計が重要です。
屋内の浴槽よりも頻繁な水質検査と清掃が必要になります。
また、以下の記事では温泉施設にもあるサウナで発生するカビ問題について紹介しています。
カビが発生する原因だけでなく、効果的な処理方法、さらには再発を防ぐための予防策まで対策方法解説しているので、併せてチェックしてみてください。
4.レジオネラ症を防ぐための対策方法
レジオネラ症を防ぐための対策方法として、以下の3つが挙げられます。
- 増殖させない
- 発生させない
- 吸い込まない
それぞれの対策について、詳しく見ていきましょう。
対策方法1.増殖させない
レジオネラ症を防ぐための対策方法の1つ目は、菌を増殖させないことです。
主に、以下の方法が効果的です。
- 適正な温度管理:60℃以上の高温にすることで菌の増殖を防ぐ
- 適切な塩素消毒:残留塩素濃度を0.2~0.4mg/Lに維持する
- バイオフィルムの除去:定期的な薬剤洗浄やブラッシング清掃を行う
塩素消毒を行う場合、塩素濃度の測定は1日に複数回行う必要があります。
また、循環配管やろ過器は、専用の洗浄剤を用いた清掃が効果的です。
対策方法2.発生させない
レジオネラ症を防ぐための対策方法の2つ目は、菌を発生させないことです。
この場合は、以下の方法を試してみましょう。
- 水の滞留を防ぐ:長期間使わない水は適宜排水する
- ろ過器・配管のメンテナンス:定期的な点検と洗浄を徹底する
- 設備の設計を見直す:菌が繁殖しにくい構造に変更する(デッドスペースを減らすなど)
長期間使用していない部屋の水栓からは使用前に十分に水を流しましょう。
また、浴槽水は毎日完全に入れ替えることが望ましいです。
デッドスペース(水が滞留する場所)を減らす際、既存の設備であれば、使用頻度の低い配管の撤去や短縮などの対策が可能です。
対策方法3.吸い込まない
レジオネラ症を防ぐための対策方法の3つ目は、菌を吸い込まないようにすることです。
以下のような対策を検討してみてください。
- エアロゾル発生を抑える:気泡発生装置やシャワーの管理を徹底する
- 利用者への注意喚起:高リスク者(高齢者・免疫力が低い人)への対策を行う
エアロゾルを防ぐためにも、気泡発生装置やジェット噴射装置は使用頻度を必要最小限にし、使用後は十分な洗浄と消毒を行いましょう。
シャワーヘッドを定期的に取り外して洗浄・消毒することや、浴室の換気を十分に行い、エアロゾルの濃度を下げることも有効です。
5.レジオネラ症の疑いがある場合の対処方法
レジオネラ症の疑いがある場合の対処方法として、以下の3つのステップが重要です。
- 保健所へ連絡
- 浴槽の使用を中止する
- 施設を現状のままにしておく
それぞれの対処方法について詳しく見ていきましょう。
対処方法1.保健所へ連絡
レジオネラ症の疑いがある場合に必要なのは、保健所への連絡です。
レジオネラ菌感染症には感染症法で定められた報告義務があるため、保健所へ速やかに相談する必要があります。
利用者から体調不良の報告があった場合や、複数の利用者が同様の症状を訴えた場合は、すぐに連絡しましょう。
保健所に連絡する際は、施設の概要、症状が出た人の人数や症状の内容、発症時期などの情報を整理しておくと、スムーズに対応できます。
必要に応じて保健所の指示のもと、水質検査や環境調査が実施されます。
検査結果が出るまでは、保健所の指示にしたがって行動しましょう。
対処方法2.浴槽の使用を中止する
レジオネラ症の疑いがある場合の対処方法の2つ目は、浴槽の使用を中止することです。
気泡発生装置やシャワーなど、エアロゾルを発生させる設備を基本とし、該当の浴槽や設備を即時使用中止します。
使用中止の案内を利用者に明確に伝え、誤って使用されないように立入禁止の表示や物理的な使用制限などの対策も効果的です。
また他の施設への影響を防ぐため、関係者へ迅速に情報共有を行いましょう。
特に同じ水源を使用している施設や、同じ管理体制の施設には優先的に連絡することが望ましいです。
対処方法3.施設を現状のままにしておく
レジオネラ症の疑いがある場合の対処方法の3つ目は、施設を現状のままにしておくことです。
原因究明のために、施設の状態を維持し、保健所の指示を待ちましょう。
特に水質検査のサンプリングが行われるまでは、浴槽水の入れ替えや設備の洗浄を行わないことが重要です。
勝手に清掃や消毒を行うと、調査ができなくなる可能性があります。
ただし、利用者の安全確保は最優先似行う必要があるため、保健所と相談しながら必要最小限の安全対策は実施しましょう。
例えば、立入禁止の措置や注意喚起の掲示などは行うべきです。
6.レジオネラ属菌の感染を防ぐため適切に対策しましょう
レジオネラ属菌による感染症は、適切な予防対策を講じることで予防できます。
予防の基本は「増殖させない」「発生させない」「吸い込まない」の3点です。
施設の規模や種類によって最適な対策は異なりますが、定期的な点検と記録の習慣化が何よりも大切です。
日常点検、定期点検、そして専門業者による検査を計画的に実施しましょう。
レジオネラ対策は一度実施して終わりではなく、継続的な取り組みが必要です。
最新の情報や技術を取り入れながら、常に改善を心がけましょう。
また、以下の記事では、私たちSpread株式会社のコラムにある「特殊清掃」に関する話題をまとめています。
孤独死や火災・水害の清掃、消臭など、さまざまな内容を紹介中です。
他にも特殊清掃に関する悩みがあれば、こちらの記事をチェックすると解決のヒントが見つけられますよ。