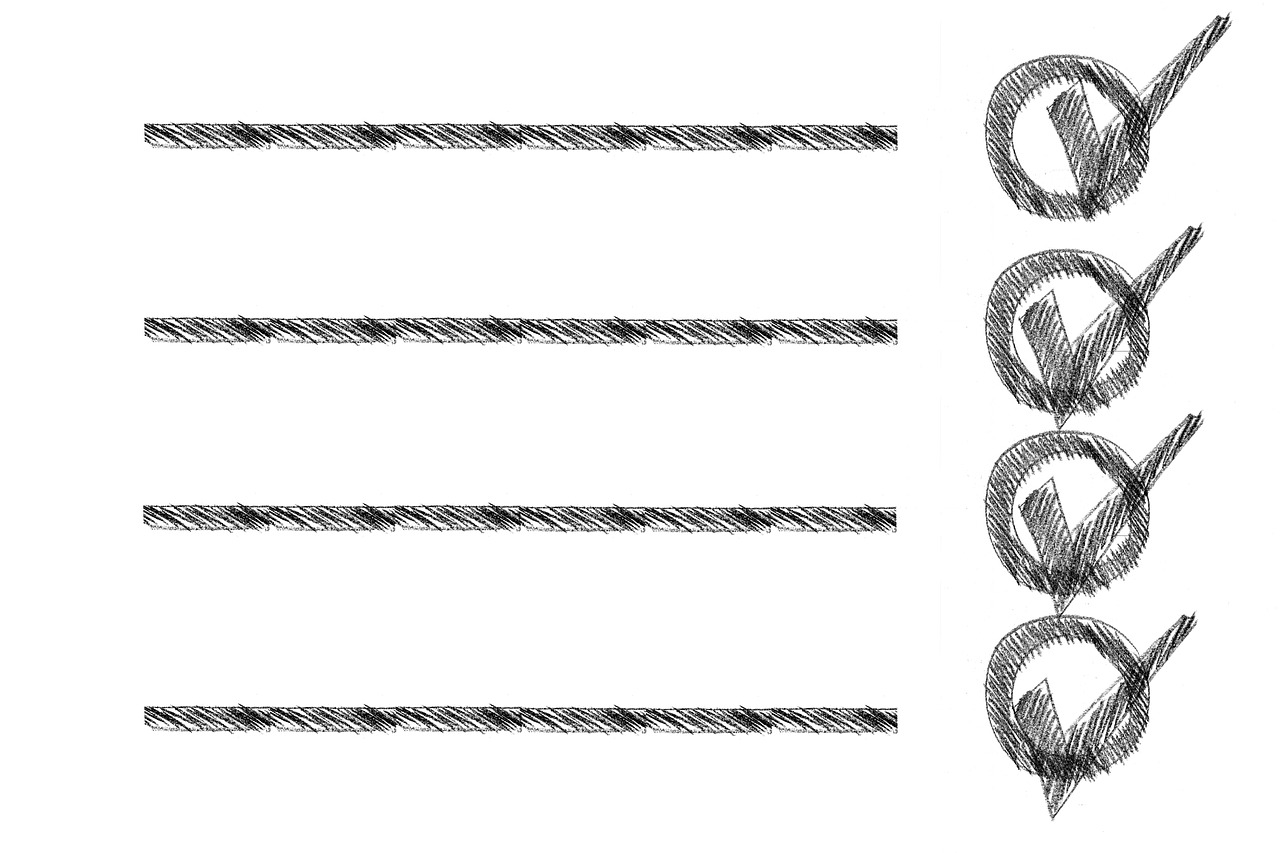「部屋に入るたび不快な臭いがして気になる」
「換気をしても消えない原因不明の臭いに悩んでいる」
「どこから発生しているのか特定できない生活臭がある」
といった悩みを抱えていませんか?
臭いの発生源は、私たちが普段気づかない場所に潜んでいることも多く、一見きれいに見える部屋でも実は意外な箇所が臭いの温床となっている可能性があります。
そこで本記事では、原因不明の部屋の臭いを特定するためのチェックポイントから、具体的な対処法、予防のためのポイントまで解説します。
部屋の臭いに悩まされている方や原因がわからず困っている方は、ぜひ最後までご一読ください。
目次
1.部屋の臭いが原因不明の場合にチェックすべき箇所
部屋の臭いが気になるものの、その原因がはっきりしない場合、以下の箇所を順番にチェックしていくことで、臭いの発生源を特定しやすくなります。
- キッチン
- トイレ
- 浴室・洗面所
- 寝具
- 排水口・排水管
- エアコン
- 収納スペース・押し入れ
- 床・壁・天井
- 家具
臭いの種類や強さによって原因箇所が異なることがあるため、下記にて詳しく見ていきましょう。
箇所1.キッチン
キッチンは食事の準備や片付けで毎日使用する場所であり、さまざまな臭いの原因となりやすい場所です。
シンクや排水溝には食べかすや油分が付着して腐敗し、不快な臭いを発生させることがあります。
更に食べかすと油分を栄養源としてカビが増殖して悪臭を放つ原因となります。
特に、シンクの下の収納スペースは水漏れや結露により、カビが発生しやすい場所なので注意が必要です。
また、生ゴミの処理が適切でない場合や、長時間放置されている場合も強い臭いの原因となります。
さらには冷蔵庫内の古い食品や、食品棚に保管している調味料などが劣化していないかもチェックが必要です。
箇所2.トイレ
トイレも、便器の縁や奥の部分には目に見えない汚れが蓄積しやすく、臭いの原因となります。
また床のタイルの目地や壁との隙間にも汚れが溜まりやすく、時間とともにカビが発生する可能性があります。
便器と便座の接合部分や床に敷いてあるトイレマット、壁紙に飛び散った尿も臭気発生の原因となります。
この部分に尿が染み込んでいると、アンモニア臭の原因となります。
換気扇のフィルターに汚れが溜まっていると臭いを除去する効果が低下するため、定期的な清掃が必要です。
箇所3.浴室・洗面所
浴室や洗面所は常に水を使用する場所であり、湿気が多いため、カビや雑菌が繁殖しやすい環境です。
特に排水口は、髪の毛や石鹸カス、皮脂などが溜まりやすく、腐敗することで不快な臭いの原因となります。
更に石鹸カスや皮脂を栄養源としてカビが発生し臭気の原因となります。
また、浴室マットや洗面所のマットの裏側は、湿気を含むためカビが発生しやすい場所です。
浴室の壁や天井、目地部分にもカビが発生することがあり、これらも臭いの原因となります。
換気扇の使用を怠ると、湿気がこもって臭いが強くなる可能性があるため注意しましょう。
箇所4.寝具
寝具類は毎日使用するため、汗や皮脂が染み込みやすく、特に注意が必要な箇所です。
枕は頭皮からの汗や皮脂、髪の毛の脂が蓄積しやすく、雑菌の繁殖を促して臭いの原因となります。
布団やマットレスも同様に、寝汗や皮脂が染み込みやすく、適切な手入れをしないとカビが発生する可能性があります。
特に梅雨時期や湿度の高い季節は危険です。
シーツや枕カバーの交換頻度が少ないと、汗や皮脂が蓄積して不快な臭いの原因となることもあるでしょう。
箇所5.排水口・排水管
排水口や排水管も、臭いの主要な発生源となることが多い場所です。
特に下水の臭いが逆流してくる場合は、排水トラップの不具合や水封部の水が少なくなっている可能性があります。
キッチンの排水口には油脂や食べかすが、浴室の排水口には髪の毛や石鹸カスが溜まりやすく、腐敗して悪臭の原因となります。
また、排水管の詰まりや汚れの蓄積によって臭いが逆流することもあるためチェックしましょう。
箇所6.エアコン
エアコンは室内の空気を循環させる役割を持つため、フィルターの汚れや内部のカビは室内全体に臭いを広げる原因となります。
特にフィルターには、ホコリや花粉、カビの胞子などが付着しやすく、湿気と結びついてカビの温床となりやすい箇所です。
カビはほこりなどの有機物にあたる栄養源がある場所に繁殖しやすいため、フィルターにたまったほこりにカビが発生し、臭いを発生させる原因となります。
また、エアコン内部の熱交換器や排水パンにもカビが発生しやすく、エアコンを運転すると臭いが室内に広がります。
長期間使用していないエアコンを久しぶりに使用するとカビ臭さを感じることがあるため、そのような場合は内部をチェックしましょう。
箇所7.収納スペース・押し入れ
収納スペースや押し入れは、換気が不十分になりやすい場所です。
特に古い衣類や布団類が湿気を含んでいると、カビの発生源となる可能性があります。
また、防虫剤や防カビ剤の使用期限が切れていたり、効果が弱まっていたりすると、衣類にカビや虫が発生しやすくなるでしょう。
収納している衣類や布団の保管中に湿気を含んでカビが発生することもあるため、チェックしてみてください。
箇所8.床・壁・天井
床や壁、天井には、目に見えない汚れや染み、カビが発生している可能性があります。
特に結露が発生しやすい場所や、日光が当たりにくい場所は要注意です。
壁紙の裏側や床下にカビが発生していると、室内全体に臭いが広がることがあります。
また、ペットの排泄物や食べこぼしなどが床材に染み込んでいると、時間の経過とともに臭いの原因になります。
さらには、壁や天井のシミは、雨漏りや結露が原因でカビを引き起こしている可能性もあるため重点的にチェックしましょう。
箇所9.家具
家具には長年の使用でさまざまな汚れや染みが付着するため、臭いの原因となります。
特にソファやカーペットなどの布製品は、飲み物をこぼした跡や食べこぼし、ペットの毛や汚れが染み込みやすく、カビの温床となる可能性があります。
また、木製家具は湿気を含むとカビが発生しやすく、特に壁際に設置している場合は要注意です。
家具の裏側や下は掃除が行き届きにくい場所のため、ホコリやカビが蓄積しやすくなっています。
2.原因不明の部屋の臭いが特定できたときの対処法
部屋の臭いの原因が特定できた場合、場所や状況に応じて適切な対処法を選ぶことが重要です。
先述した9つの箇所について、それぞれ効果的な対処法を解説します。
- キッチン
- トイレ
- 浴室・洗面所
- 寝具
- 排水口・排水管
- エアコン
- 収納スペース・押し入れ
- 床・壁・天井
- 家具
下記にて、詳しく見ていきましょう。
1.キッチンの臭い対策
| 対象箇所 | 対処方法 | 使用するもの |
| 排水溝 | 1. 重曹を振りかける 2. 酢を注いで発泡させる 3. 熱湯で流す 4. 週1回の定期実施 | 重曹、酢、パイプクリーナー |
| 生ゴミ | 1. こまめな処分(夏場は毎日) 2. ゴミ箱の定期洗浄 3. 水切りの徹底 4. 消臭剤の使用 | 中性洗剤、水切りネット、消臭剤 |
| 冷蔵庫 | 1. 週1回の食品チェック 2. 3ヶ月に1回の大掃除 3. 消臭剤の設置 4. 野菜室の清掃 | 冷蔵庫用消臭剤、専用洗剤 |
キッチンの臭い対策でもっとも重要なのは、「予防」と「定期的なメンテナンス」です。
特に排水溝は一度詰まりや臭いが発生すると対処が困難になるため、予防的な清掃を習慣化することが大切です。
生ゴミの管理については、水分量を減らすことが腐敗防止の鍵となります。
水切りを徹底し、生ゴミ用の密閉容器の使用も検討してください。
また冷蔵庫は密閉空間であるため、一度臭いが染み付くと除去が難しくなります。
食品の期限管理と併せて、棚板や野菜室の清掃も定期的に行うことで、臭いの発生を未然に防ぐことができます。
特に夏場は食品の管理を徹底し、開け閉めの回数も必要最小限に抑えましょう。
2.トイレの臭い対策
| 対象箇所 | 対処方法 | 使用するもの |
| 便器・タンク | 1. 専用洗剤での徹底洗浄 2. 裏側・縁の重点清掃 3. 床との隙間も除菌 4. 週2回以上の定期清掃 | トイレ専用洗剤、除菌用エタノール、ブラシ、クエン酸、酸性洗剤 |
| 床・壁 | 1. 週1回の拭き掃除 2. 目地の重点清掃 3. 除菌液での除菌 4. 乾燥の徹底 | 除菌クリーナー、モップ、雑巾、クエン酸、酸性洗剤 |
| 換気設備 | 1. 換気扇の定期清掃 2. フィルター交換 3. 24時間換気の活用 4. 窓の定期開放 | 換気扇専用洗剤、新しいフィルター |
トイレの臭い対策は、単なる清掃だけでなく、「除菌」と「換気」の3要素がポイントとなります。
特に便器と床の境目、便器と便座の間、タンク背面など、普段目につきにくい場所にこそ臭いの原因が潜んでいることが多いため、重点的な清掃が必要です。
消臭剤や芳香剤は、あくまでも補助的な対策として考え、まずは物理的な清掃と除菌を徹底することが重要です。
清掃では、尿の臭気の原因でもあるアンモニアという成分はアルカリ性のため、クエン酸や酸性洗剤などを使用し臭気成分を中和させて消臭することが必要です。
また、24時間換気システムがある場合は積極的に活用し、定期的な窓開けと組み合わせることで、より効果的な消臭作用が期待できます。
湿気がこもりやすい場所でもあるため、掃除後の乾燥も忘れずに行いましょう。
3.浴室・洗面所の臭い対策
| 対象箇所 | 対処方法 | 使用するもの |
| 排水口周り | 1. カバーを外して清掃 2. 髪の毛・汚れ除去 3. カビ取り剤使用 4. 防カビ剤の塗布 | カビ取り剤、防カビ剤、排水口ネット |
| 壁・天井 | 1. カビの除去・清掃 2. 防カビ剤の塗布 3. 換気の徹底 4. 週1回のチェック | カビ取り剤、防カビ剤、スポンジ |
| 備品類 | 1. 洗面器・風呂椅子の洗浄 2. マットの定期洗濯 3. シャワーヘッドの清掃 4. 石鹸カスの除去 | 中性洗剤、クエン酸、漂白剤 |
浴室・洗面所の臭い対策でもっとも重要なのは、「カビ対策」と「水回りの乾燥管理」です。
カビは一度発生すると完全な除去が難しく、健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。
そのため、予防的な対策を心がけることが特に重要です。
具体的には、使用後の換気を徹底し、壁や天井の水滴は可能な限り拭き取りましょう。
また、排水口は髪の毛や皮脂などの汚れが溜まりやすい場所であるため特に注意が必要です。
専用のネットを使用し、週1回以上の清掃を習慣化することで、悪臭の発生を防げます。
備品類の清掃も重要で、特に洗面器や風呂椅子は裏側にカビが発生しやすいため、定期的な天日干しと洗浄を行いましょう。
4.寝具の臭い対策
| 対象物 | 対処方法 | 使用するもの |
| 布団・マットレス | 1. 定期的な天日干し(月1~2回) 2. 重曹での消臭処理 3. 両面の徹底乾燥 4. プロのクリーニング(年1~2回) | 重曹、布団たたき、布団乾燥機 |
| 枕 | 1. カバーの週1回洗濯 2. 本体の天日干し 3. 防ダニスプレーの使用 4. 定期的な買い替え | 洗剤、防ダニスプレー、枕カバー |
| 防ダニ対策 | 1. 防ダニカバーの使用 2. 週1回の掃除機がけ 3. 湿度管理(50~60%) 4. 3ヶ月に1回の丸洗い | 防ダニカバー、掃除機、除湿機 |
寝具の臭い対策は、「清潔さの維持」と「ダニ・カビの予防」が重要です。
人は1日の3分の1を寝具で過ごすため、健康面でも適切な管理が欠かせません。
特に汗や皮脂は寝具に染み込みやすく、放置すると雑菌の温床となってしまいます。
定期的な天日干しは、紫外線による除菌効果と湿気除去の両面で効果的です。
ただし、梅雨時期や花粉の時期は、室内干しと布団乾燥機の併用がおすすめです。
また、マットレスなど重いものは自宅での手入れが難しい場合があるため、年に1~2回はプロのクリーニングを検討しましょう。
5.排水口・排水管の臭い対策
| 対象箇所 | 対処方法 | 使用するもの |
| 表面の清掃 | 1. ネット・カバーの洗浄 2. 目に見える汚れの除去 3. 消臭剤の使用 4. 週2~3回の定期清掃 | 排水口ネット、ブラシ、消臭剤 |
| 配管内部 | 1. 重曹と酢での洗浄 2. 熱湯での流し込み 3. 酵素系洗剤の使用 4. 専門業者による高圧洗浄 | 重曹、酢、パイプ用洗剤 |
| 予防策 | 1. 食べ物の流入防止 2. 髪の毛の除去 3. 定期的な換気 4. 月1回の徹底洗浄 | 細目ネット、換気扇、防臭剤 |
排水口・排水管の臭い対策では、「定期的な清掃」と「予防的なメンテナンス」の2つを心がけることが重要です。
特に排水管は一度詰まりが発生すると解消が困難になる場合が多いため、予防が極めて重要です。
日常的なケアとしては、排水口ネットの使用と定期的な清掃が基本となりますが、それだけでは配管内部の汚れは完全には防げません。
そのため、月1回程度は重曹と酢を使用した洗浄を行い、年に1回程度は専門業者による高圧洗浄を検討することをおすすめします。
6.エアコンの臭い対策
| 対象箇所 | 対処方法 | 使用するもの |
| フィルター | 1. 2週間に1回の清掃 2. 中性洗剤での洗浄 3. 完全乾燥の確認 4. 傷みの確認と交換 | 中性洗剤、ブラシ、新品フィルター、掃除機 |
| 内部機器 | 1. 専門業者による清掃 2. カビ取り剤の使用 3. 送風運転での乾燥 4. 定期点検の実施 | カビ取り剤、エアコン洗浄剤 |
| 使用方法 | 1. 2時間ごとの換気 2. 適切な温度設定 3. 湿度管理の徹底 4. 就寝時の自動運転 | 温湿度計、タイマー |
エアコンの臭い対策では、「定期的なメンテナンス」と「適切な使用方法」が鍵となります。
特に注意すべきは、フィルターや内部に付着したカビや細菌がエアコン使用時に室内に拡散される可能性があることです。
フィルターに溜まったほこりを掃除機などで除去し、カビの発生を予防することで、臭気の発生を予防する必要があります。
フィルターの清掃は自己管理できますが、内部のクリーニングは素人による無理な分解清掃で故障の原因となる可能性があるため、年1回程度の専門業者による清掃をおすすめします。
また、エアコン使用時は定期的な換気を行い、室内の湿度管理にも気を配ることで、カビの発生を予防できます。
冷房使用時は室内の温度が極端に下がりすぎないよう、外気温との差を5~6度程度に設定することも重要です。
7.収納スペース・押し入れの臭い対策
| 対象箇所 | 対処方法 | 使用するもの |
| 収納空間全般 | 1. 定期的な換気(週1~2回) 2. 除湿剤の効果的配置 3. 棚板の清掃 4. 床面の掃除機がけ | 除湿剤、掃除機、モップ、サーキュレーター |
| カビ対策 | 1. エタノールでの拭き取り 2. 防カビ剤の塗布 3. 通気性の確保 4. 床下換気の点検 | 除菌用エタノール、防カビ剤、換気扇 |
| 収納物管理 | 1. 季節ごとの整理 2. 防虫剤の設置 3. 収納物の適切な間隔 4. 使用前の天日干し | 防虫剤、消臭剤、収納ケース |
収納スペースの臭い対策でもっとも重要なのは、「湿気対策」です。
密閉された空間は湿気がこもりやすく、カビや雑菌の温床となりやすいため、定期的な換気と除湿が欠かせません。
特に和室の押し入れは、畳からの湿気も影響するため、床下の換気状態にも注意が必要です。
サーキュレーターなどを使用して収納スペース内の空気循環を行い湿気を滞留させないなどの対策を取りましょう。
また、収納物は詰め込みすぎず、適度な空間を設けることで空気の循環を促進できます。
季節の変わり目には収納物の総点検を行い、カビや虫害の早期発見に努めましょう。
防虫剤や除湿剤は、効果が切れる前に定期的な交換を心がけることが重要です。
8.床・壁・天井の臭い対策
| 対象箇所 | 対処方法 | 使用するもの |
| 床材 | 1. 素材に応じた洗剤選択 2. 目地の重点清掃 3. クエン酸での拭き掃除 4. 定期的なワックス掛け | 中性洗剤、クエン酸、ワックス |
| 壁紙 | 1. 重曹水での部分清掃 2. 換気の徹底 3. シミの早期対処 4. 必要に応じた張替え | 重曹、スプレーボトル、雑巾 |
| 天井 | 1. 埃の除去 2. カビの点検・対処 3. 換気扇周りの清掃 4. 結露対策の実施 | はたき、カビ取り剤、除湿機 |
床・壁・天井の臭い対策は、「素材に応じた適切なケア」と「湿気・結露対策」が重要です。
特に壁紙は水分に弱いため、清掃時は水分量に気を付ける必要があります。
まずは目立たない場所でテストを行ってから実施しましょう。
また温度差による結露もカビの発生原因となるため、室内の温度と湿度の管理が重要です。
冬場は暖房使用時の換気を忘れずに行い、必要に応じて除湿機の使用も検討しましょう。
また、定期的な点検により、劣化やカビの発生を早期に発見することも大切です。
9.家具の臭い対策
| 対象物 | 対処方法 | 使用するもの |
| 布製品 | 1. 掃除機での定期清掃 2. 重曹による消臭 3. 専門クリーニング 4. カバーの定期洗濯 | 掃除機、重曹、消臭スプレー |
| 木製家具 | 1. 乾拭き→湿拭き 2. 通気性の確保 3. 防カビ剤の使用 4. 定期的なメンテナンス | 専用クリーナー、防カビ剤、乾いた布 |
| レザー製品 | 1. 専用クリーナーでの拭き取り 2. 革専用保湿剤の使用 3. 直射日光を避ける 4. 定期的な革メンテナンス | 革専用クリーナー、保湿剤、柔らかい布 |
家具の臭い対策には、「素材別の適切なケア」と「定期的なメンテナンス」が重要です。
特にソファなどの大型の布製品は、家庭での完全なクリーニングが難しいため、年1~2回の専門クリーニングを検討することを推奨します。
木製家具は湿気に弱いため、拭き掃除後は必ず乾拭きを行い、水分を残さないようにしましょう。
また、レザー製品は乾燥による劣化を防ぐため、定期的な保湿ケアが必要です。
いずれの素材も、直射日光や暖房機器からの熱は劣化を促進するため、設置場所や環境にも注意を払いましょう。
特に高価な家具は、メーカー推奨のケア用品を使用することで長期的な品質維持が可能です。
また、以下の記事では部屋のカビ臭対策について紹介しています。
放置するリスクや、除去・予防する際の注意点についても解説しているので、併せてご確認ください。
3.原因不明の部屋の臭いが特定できない場合の対処法
原因不明の部屋の臭いが特定できない場合の対処法は、以下の2つです。
- 再度部屋を確認する
- 専門家の調査を依頼する
それぞれ解説します。
対処法1.再度部屋を確認する
まずは自分でできる確認作業を徹底することが重要です。
特に見落としがちな場所として、大型家具の裏側や床下、天井裏などがあります。
これらの場所は日常的に目が届きにくく、カビや害虫の温床になっている可能性が高いため、入念なチェックが必要です。
臭いの特徴を詳しく記録することも、解決へのポイントとなります。
時間帯による臭いの強さの変化は、発生源を特定する重要な手がかりとなります。
例えば、朝方に臭いが強くなる、夜になると臭いが気になり始めるなど、具体的な変化をメモに残しておきましょう。
対処法2.専門家の調査を依頼する
専門家による調査は、原因不明の臭いを特定するもっとも確実な方法の1つです。
専門家は特殊な機器や経験に基づく知識を活用して、一般人では気づきにくい臭いの原因を特定できます。
例えば、建物の構造上の問題や配管の不具合など、目に見えない部分に潜む原因も特定可能です。
なお、専門家の調査を依頼する際は、複数の業者から見積もりを取りましょう。
業者によって得意分野や使用する機器が異なることがあるため、臭いの種類や状況に応じて最適な業者を選ぶことが重要です。
また、調査後の対策まで含めた総合的な提案をしてくれる業者を選ぶと、より確実な解決が期待できます。
なお、調査費用は業者によって異なりますが、根本的な解決のための投資と考えることが大切です。
臭いの原因を特定し、適切な対策を講じることで、快適な住環境を取り戻せるでしょう。
4.原因不明の部屋の臭いを防ぐポイント
原因不明の部屋の臭いを防ぐためには、日常的なケアと適切な対策が重要です。
快適な室内環境を維持するための主要なポイントは以下の3つです。
- 掃除とメンテナンスを欠かさない
- こまめな換気を心がける
- 消臭機を設置する
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
ポイント1.掃除とメンテナンスを欠かさない
快適な室内環境を保つためには、定期的な掃除とメンテナンスが欠かせません。
床や排水口、家具の裏側など、普段目につきにくい場所にも臭いの原因となる汚れが蓄積しやすいため、週1回程度の定期清掃を心がけましょう。
特にエアコンや洗濯機などの家電製品は、フィルターや内部に埃や雑菌が溜まりやすく、放置すると不快な臭いの原因となります。
エアコンは2週間に1回程度のフィルター清掃、年1回の内部クリーニングを推奨します。
洗濯機は月1回程度の槽洗浄を行い、カビや雑菌の繁殖を防ぎましょう。
汚れが頑固な場合や自力での清掃が難しい場合は、専門のクリーニング業者に依頼することをおすすめします。
定期的なメンテナンスは臭いの予防だけでなく、機器の寿命を延ばすことにもつながります。
ポイント2.こまめな換気を心がける
室内の空気を清浄に保つためには、計画的な換気が重要です。
特に朝と夕方など、外気との温度差が少ない時間帯を選んで換気を行うことで、効率的に室内の空気を入れ替えられます。
なお窓を開けて行う自然換気の際は、対角線上の窓を開けて空気の流れを作ることでより効果的な換気が可能です。
換気扇は湿気や臭い物質を外部に排出する重要な役割を果たすため、調理や入浴後には必ず換気扇を使用しましょう。
また、換気扇自体も定期的な清掃が必要です。
フィルターや羽根に付着した油汚れや埃を放置すると、換気効率が低下するだけでなく、臭いの原因にもなるためです。
24時間換気システムが設置されている場合は常時運転を心がけ、フィルターの清掃も忘れずに行いましょう。
ポイント3.消臭機を設置する
空気清浄機や消臭機の設置は、部屋の臭い対策として効果的な方法です。
最新の空気清浄機は、微細な粒子や臭い物質を効率的に除去する高性能フィルターを搭載しており、室内の空気質を改善する効果が期待できます。
選び方のポイントは、部屋の広さに合った適切な処理能力を持つ機種を選ぶことです。
また、活性炭フィルターや光触媒、プラズマクラスターなどの消臭技術を備えた機種を選ぶことで、より効果的に臭いを分解・除去できます。
設置場所は、部屋の中央付近か、臭いが気になる場所の近くに置くことをおすすめします。
ただし、消臭機に頼りすぎず、定期的な掃除や換気も心がけてください。
5.部屋から原因不明の臭いがするときは適切に対処しよう
部屋の原因不明の臭いは、生活の質を大きく低下させる厄介な問題です。
原因不明の臭いがするときに重点的にチェックすべき箇所は次のとおりです。
- キッチン
- トイレ
- 浴室
- 寝具
- 排水口
- エアコン
- 収納スペース
- 床や壁
- 家具
臭いの特徴や強さ、時間帯による変化なども、原因特定の重要な手がかりとなります。
原因が特定できた場合は、それぞれの箇所に適した対処法を実施しましょう。
定期的な清掃や換気、適切なメンテナンス、専門的なクリーニングなど、状況に応じた対策を講じることが大切です。
一方、自己解決が難しい場合は、専門家への相談をおすすめします。
プロの業者や専門家は、経験と専門知識を活かして的確な原因特定と解決策を提案してくれます。
また、私たちSpread株式会社のコラムで紹介している「消臭」に関する話題をまとめたものが以下の記事です。
タバコ・ペット・生活臭などの臭い対策を幅広く取り上げています。
他にも消臭に関する悩みがあれば、ぜひチェックしてみてください。