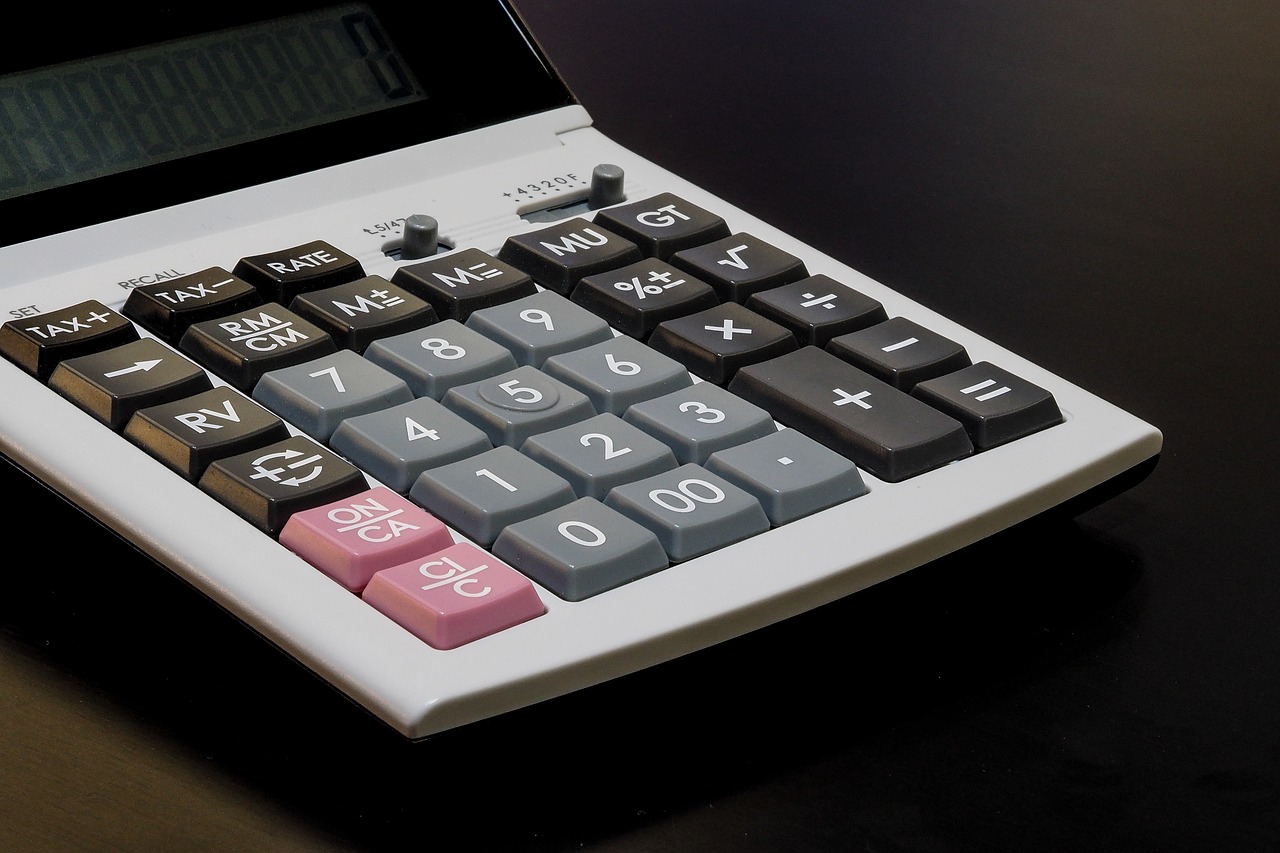「火災で燃えた家具や建材をどう処分すればいいのか分からない」
「自治体の収集ルールが複雑で困っている」
「業者に依頼すべきか迷っている」
といった悩みを抱えている方は少なくありません。
火災ごみの処分は、自治体から収集を拒否されたり、思わぬ追加費用が発生したりするなど、混乱が生じやすいのです。
また、燃え残りの建材には有害物質が含まれている可能性もあり、安全面での配慮も必要です。
そこで本記事では、火災ごみの基本的な処分方法から、自力での片付け方、業者への依頼が必要なケースまでをまとめました。
さらに、処分費用の目安や抑える方法についても詳しく説明します。
火災後の片付けに直面している方、今後の対策として知識を得たい方は、ぜひ最後までご一読ください。
目次
1.火災ごみは通常のごみと同じように処分できる?
火災により発生したごみの処分方法は、以下の2つのケースにわけて考える必要があります。
- 家庭内で発生した火災ごみの場合
- 事業所や工場などで発生した火災ごみの場合
それぞれのケースで適用される法律や処理方法が異なるため、状況に応じた対応が求められます。
以下にて、各ケースについて詳しく見ていきましょう。
ケース1.家庭内で発生した火災ごみの場合
家庭内で発生した火災ごみは、一般廃棄物として自治体が処理を行うケースがほとんどです。
ただし、通常の家庭ごみとは異なり、特別な対応が必要になります。
そのためまずは自治体の窓口に火災発生の報告を行い、処理方法について相談することが重要です。
多くの自治体では、罹災証明書の提出により処理手数料が減免される制度を設けています。
また、分別方法も自治体によって細かく規定されており、可燃物・不燃物・金属類など、材質ごとに分別する必要があります。
特に、家電リサイクル法対象製品や処理困難物が含まれている場合は、別途専門の処理ルートを確保しましょう。
ケース2.事業所や工場などで発生した火災ごみの場合
事業所や工場で発生した火災ごみは、廃棄物処理法上の産業廃棄物として扱われます。
そのため、一般廃棄物とは異なり、専門の処理業者に委託して処分する必要があります。
処分にあたっては、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の発行が必要で、適正な処理を確認しなければなりません。
特に工場などでは、危険物や有害物質が含まれている可能性を捨てきれないため、処理前に専門家による調査が必要になることもあります。
また、火災保険に加入している場合は、処理費用が補償される可能性があるため保険会社への連絡も必要です。
処分時には環境への配慮も必要なため、可能なものはリサイクルするよう努める必要があります。
2.火災ごみの処分費用の目安
ここでは、それぞれのケースにおける処分費用の目安について詳しく解説します。
- 自力で片づける場合
- 業者に依頼する場合
火災ごみの処分費用は、自力で行うか業者に依頼するかで大きく変わってきます。
ケースごとに具体的な費用を見ていきましょう。
ケース1.自力で片づける場合
自力で火災ごみを処分する場合、主な費用は必要な道具や消耗品の購入費用と、自治体に支払う処理費用です。
まず、ごみ袋や軍手、マスクなどの基本的な道具・消耗品を購入するためには1,000円から5,000円程度の費用がかかります。
自治体への処理費用は地域によって料金体系が異なりますが、一般的に数千円から数万円の範囲です。
ただし、罹災証明書を取得することで、処理費用が減免される自治体もあります。
このように自力での処分は費用を抑えられる反面、労力と時間がかかることを考慮に入れる必要があります。
また、分別作業や運搬時の安全確保のため、必要に応じて防護具や運搬用具のレンタル費用も考慮しましょう。
レンタルをする場合、1日あたり数千円程度の追加費用が必要です。
ケース2.業者に依頼する場合
業者に火災ごみの処分を依頼する場合、費用は搬出量や被害規模によって大きく変動します。
もっとも一般的な料金体系はトラックの積載量に応じた設定となっており、軽トラック1台分で約45,000円から75,000円、中型トラック1台分では約100,000円から150,000円が目安です。
ただし、火災ごみの撤去、分別、運搬、処分場への持ち込みなどを依頼する場合はさらに費用がかかることもあります。
例えば30坪2階建ての木造住宅全体が被災した場合は、地域や業者によっても大きく異なりますが、処分費用はおよそ100万円から400万円になります。
火災保険に加入している場合は、保険金で費用をカバーできる可能性があるため、保険会社への確認も重要です。
見積もりを取る際は、作業内容と料金の内訳を詳しく確認することをおすすめします。
3.火災ごみの処分費用を抑える方法
火災ごみの処分には、予想以上の費用がかかることがあります。
しかし、以下のような方法を取ることで、処分費用を抑えられる可能性もあります。
- なるべく自力で廃材を処理する
- 火災現場に特化した業者を利用する
火災ごみの処分費用を抑えるための具体的な方法について、以下で詳しく見ていきましょう。
方法1.なるべく自力で廃材を処理する
火災ごみの処分費用を抑えるには、可能な限り自力での処理を検討しましょう。
小型の家具や可燃ごみなどは、自治体の収集ルールにしたがって処分できるため、分別して出すことで費用を抑えられます。
ただし、このような自力での処理には体力的な負担や時間がかかることには注意が必要です。
なお、罹災証明書があれば通常の粗大ごみ処理手数料を免除できることもあります。
火災現場の清掃や自力での処理を選ぶ際は、安全面にも十分注意を払いましょう。
焼け残りの建材などには鋭利な部分があり、けがのリスクがあります。
他にもダイオキシンなど有害物質もありますので、体調面などのリスクも高まります。
また、一度に大量の処分をする場合は、近隣への配慮も忘れずに計画的に進めることが大切です。
方法2.火災現場に特化した業者を利用する
火災現場の清掃や廃材処理に特化した業者を利用することで、効率的かつ経済的な処分が可能になります。
専門業者は、火災現場特有の問題に精通しており、適切な処理方法を提案してくれます。
また、一般の廃棄物処理業者と比べて、作業効率が良く総合的なコストを抑えやすいのも魅力です。
見積もりを取る際は、複数の業者に依頼して比較検討することが重要です。
その際、作業内容や処分方法の詳細、追加料金の有無などをしっかりと確認しましょう。
火災保険の適用範囲内であれば、保険会社に相談して推奨される業者を紹介してもらうことも検討できます。
また、火災現場専門の業者は、消火活動による水濡れの処理や、煤煙の除去など、火災後の特殊な清掃にも対応できます。
建物の修復や再使用に向けた準備も同時に進めることができ、トータルでの費用削減につながるでしょう。
以下の記事では、火災事故が起きた現場の特殊清掃について詳しく紹介しています。
プロが行っている清掃の方法について解説しているので、ぜひチェックしてみてください。
火災事故の特殊清掃とは?作業内容・費用・業者選びのポイントを解説
4.火災ごみを自力で処分するときの注意点
火災ごみを自力で処分する際は、以下の5つのポイントを押さえることで、安全かつ適切な処分が可能になります。
- 自治体の分別方法を守る
- 収集・搬出方法を守る
- 罹災証明書を取得する
- 処分できないごみが含まれていないか確認する
- 無理な運搬を避ける
それぞれ解説します。
注意点1.自治体の分別方法を守る
火災ごみの処分時は、まず自治体の定める分別ルールを確認することが重要です。
自治体によって火災ごみの分類や収集方法が異なるため、必ず事前に公式ホームページで確認するか、窓口に問い合わせましょう。
基本的には、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、危険物などのカテゴリーがあります。
燃え残った木材や布類は可燃ごみ、金属類は不燃ごみ、大型の家具や建材は粗大ごみとしての分類です。
また、スプレー缶やライターなどの危険物は、特別な処理が必要になります。
分別方法を守ることで、スムーズな収集と適切なリサイクルを心がけましょう。
注意点2.収集・搬出方法を守る
火災ごみの収集・搬出には、通常のごみとは異なる特別なルールが設けられています。
多くの自治体では、特別収集日を設定しているか、指定の廃棄場所への持ち込みを求めています。
持ち込みの場合は予約が必要となりやすく、処理料金が発生することも少なくありません。
また、搬出時には指定の袋や、シートで包むなどの決まりもあります。
大量の火災ごみを一度に出す場合は、事前に自治体と相談し、収集方法や日程を調整しましょう。
注意点3.罹災証明書を取得する
火災ごみの処分では、「罹災証明書」の取得が重要です。
この証明書は、火災による被害を公的に証明する書類で、消防署や市区町村の窓口で申請できます。
多くの自治体では、この証明書の提示により、火災ごみの処理が無料になったり、処理料金が割引されたりします。
申請の際は、火災の発生日時、場所、被害状況などの情報が必要です。
また、火災保険の請求時にも必要となるため、できるだけ早めに取得することをおすすめします。
証明書の有効期限や使用できるサービスは自治体によって異なるため、詳細は窓口で確認しましょう。
注意点4.処分できないごみが含まれていないか確認する
火災現場から出るごみの中には、以下のように自治体では処理できない特殊な廃棄物が含まれている可能性があります。
- アスベストを含む建材
- 有害な化学物質
- 特定の電化製品(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機など)
環境や健康に悪影響をおよぼす可能性があるため、これらの処分は専門の処理業者に依頼する必要があります。
処分できないごみが含まれていないかの確認ができない場合や処理方法が分からない場合は、自治体の環境課や専門業者に相談することをおすすめします。
注意点5.無理な運搬を避ける
火災ごみの中には、大型の家具や重い建材が含まれていることが多く、運搬時の事故や怪我のリスクが高まります。
腰痛や関節の損傷を防ぐため、無理な運搬は避けましょう。
大型の家具や重い建材を運ぶ際は、台車やロープなどの道具を活用し、必要に応じて周囲の協力を得ることが重要です。
また、一人では運べない大型のごみは、搬出の補助サービスを利用することも検討してください。
安全な作業のためには、適切な作業着や手袋を着用し、天候の良い日を選んで作業を行うことも推奨されます。
焦って作業を進めるのではなく、計画的に処分を進めることが重要です。
5.火災ごみの処分を業者に依頼すべきケース
火災ごみの処分は、状況によって専門業者への依頼が必要になるケースがあります。
- ごみの量が大量な場合
- 特殊な廃棄物が含まれている場合
- 火災後の清掃を含めた作業が必要な場合
- 自治体が対応できない場合
- 火災後の清掃を含めた作業が必要な場合
上記のような場合は、業者への依頼を検討しましょう。
ケース1.ごみの量が大量な場合
火災により大量の廃棄物が発生した場合、自力での処分は困難を極めます。
特に、大型の家具や家電製品、建材などは重量があり、一般家庭での運搬は危険を伴います。
また、自治体の通常の収集では対応できないサイズや量の場合も多く、特別な対応が必要です。
このような場合、産業廃棄物処理の許可を持つ専門業者に依頼することで、安全かつ効率的な処分が可能になります。
業者は必要な重機や運搬車両を保有しており、大量の廃棄物でも一括で処理できます。
さらに、分別作業も専門的な知識にもとづいて行われるため、リサイクル可能な物品も適切に選別可能です。
ケース2.特殊な廃棄物が含まれている場合
火災現場には、一般廃棄物として処理できない特殊な廃棄物が含まれていることがあります。
特にアスベストを含む建材や有害な化学物質が付着した物品は、専門的な処理が必要です。
また、家電リサイクル法対象製品や自動車用バッテリーなども、特定のリサイクルルートでの処理が義務付けられています。
この特殊廃棄物は、取り扱いを誤ると健康被害や環境汚染のリスクがあります。
その点、専門業者は適切な保護具を使用し、法令に従った処理方法を熟知しているため、リスクもに配慮できます。
廃棄物の種類に応じた処理施設への運搬ルートも確立されているため、安全かつ確実な処分が可能です。
ケース3.火災後の清掃を含めた作業が必要な場合
火災後の建物内には、煤や有害物質が付着している可能性があります。
一般的な清掃用具では完全な除去が困難で、専門的な洗浄作業が必要になるため、専門業者への依頼が不可欠です。
また、火災による臭気は建材に深く染み込んでおり、特殊な消臭処理が必要な場合もあります。
専門業者は高圧洗浄機や特殊な洗剤、消臭装置など、プロ仕様の機材を使用して清掃を行うため、高い消臭効果が期待できるのです。
また、清掃と廃棄物処理を同時に行うことで、作業の効率化とコスト削減も期待できます。
ケース4.自治体が対応できない場合
自治体の一般廃棄物処理施設では受け入れできない種類や量の火災ごみは、専門業者への依頼が必要です。
例えば、大規模な火災で発生した建材や、事業所からの産業廃棄物に該当する物品などが該当します。
このような場合、産業廃棄物処理業の許可を持つ専門業者に依頼することで、適切な処理が可能です。
業者は廃棄物の種類や性状に応じた処理施設との連携体制を整えており、法令に準拠した処分方法を提案してくれます。
また、マニフェスト制度に基づく適正処理の証明書類も発行されるため、処分の透明性も確保できます。
ケース5.火災後の清掃を含めた作業が必要な場合
火災による被害は、単なるごみの処分だけでなく、建物全体の清掃や修復を必要とします。
煤や焦げの付着、消火活動による水濡れ、異臭の発生など、複合的な問題に対処する必要があるためです。
このような場合、火災復旧の専門業者に依頼することで、清掃から廃棄物処理まで一貫した対応が期待できます。
また、保険会社との折衝もサポートしてくれる業者も多く、スムーズな復旧作業が期待できます。
6.火災ごみは状況に応じた適切な方法で処分しよう
火災ごみの処分方法は、発生場所や状況によって大きく異なります。
処分費用は自力で行う場合、数千円から数万円で済みますが、業者に依頼する場合は規模や内容によって数万円から数十万円の費用が発生します。
費用を抑えるためには、可能な範囲で自力での処理を検討し、必要に応じて火災現場に特化した業者を選ぶことが重要です。
ただし、ごみの量が大量な場合や特殊な廃棄物が含まれている場合、火災後の清掃作業が必要な場合は、無理せず専門業者への依頼を検討しましょう。
また、私たちSpread株式会社のコラムにある「火災復旧」に関する情報をまとめたものが以下の記事です。
火災後の清掃・修繕・有害物質除去・費用相場など、幅広い内容を紹介しています。
他にも火災復旧に関する疑問や悩みがあれば、こちらの記事をチェックしてみてください。