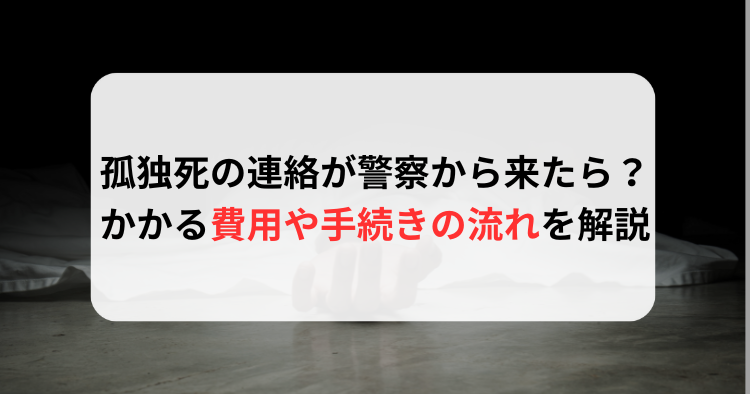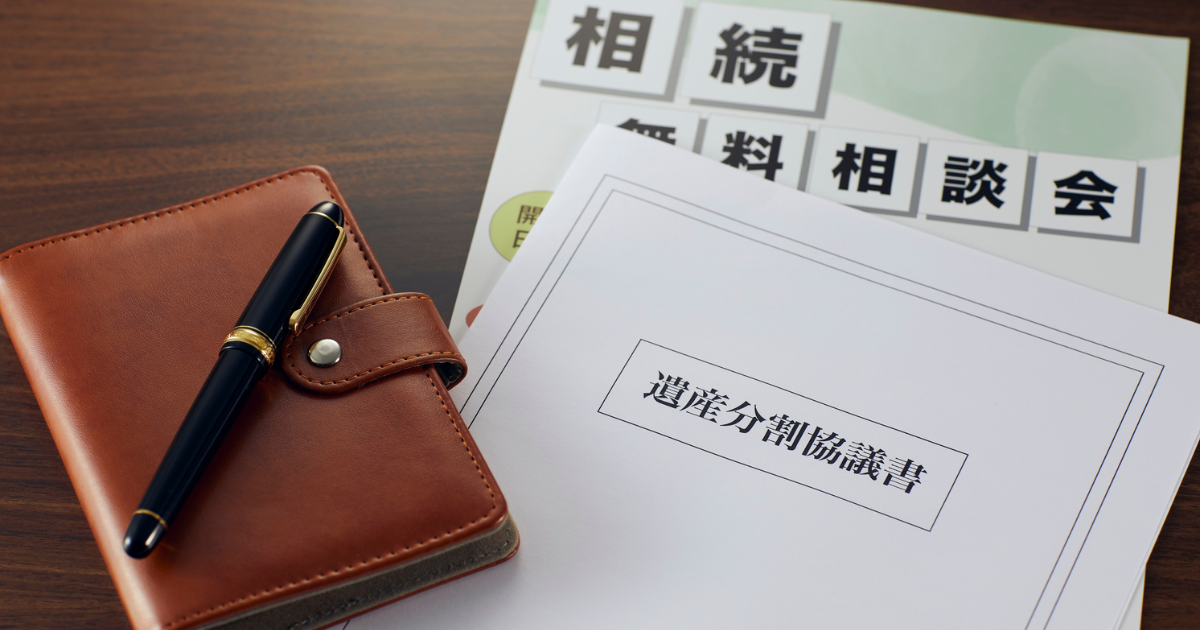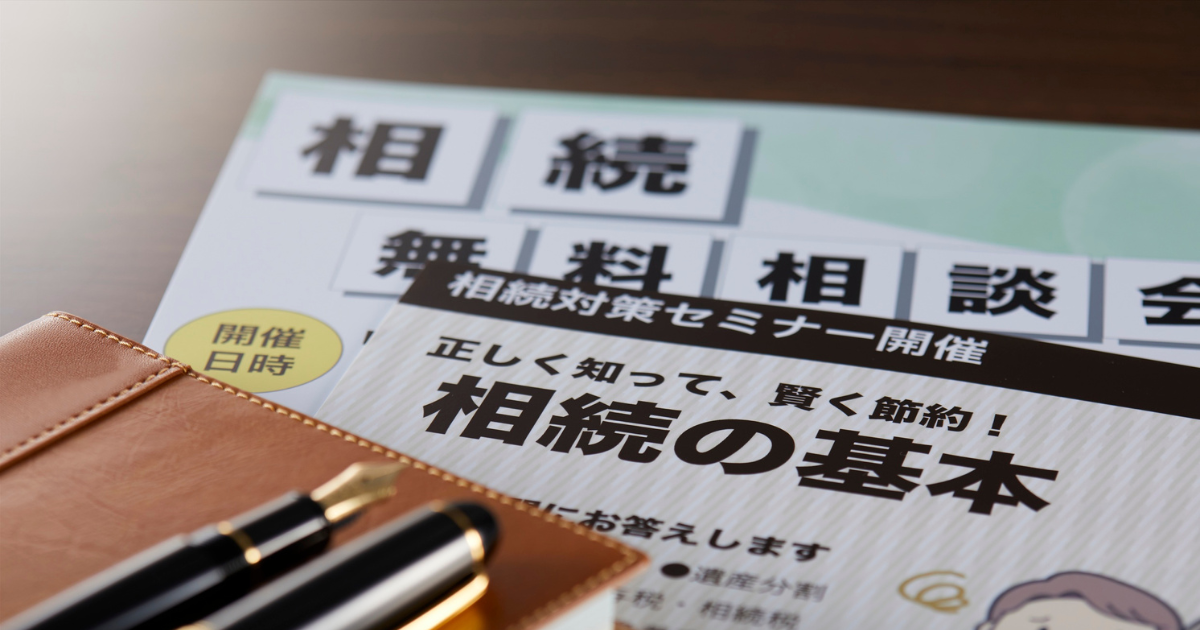「警察から身内が孤独死したと連絡が…」
突然の知らせに現実を受け止めきれない混乱の中で、何をすべきか戸惑っていませんか?
警察の対応や必要な手続き、費用の問題など、頭の中は疑問と不安でいっぱいでしょう。
そこでこの記事では、孤独死発見後の手続きで警察に支払う費用や、遺族が行うべき手続きの流れなどを分かりやすく解説します。
【孤独死の手続き・清掃】専門業者が迅速対応!
突然、警察から「身内が孤独死した」との連絡が…何をすべきか分からず、不安を感じていませんか?
当社は、特殊清掃・遺品整理・消臭・感染防止を専門に対応。
専用の薬剤を使用し、短時間で完全消臭・原状回復を実現します。
24時間受付・最短即日対応! まずは無料相談をご利用ください。
専門技術 × 幅広い対応!特殊清掃・カビ除去・災害復旧・お片付け清掃もおまかせください!
目次
1.親族が孤独死したと警察の連絡を受けてから葬儀までの流れ
親族が孤独死した場合、警察からの連絡を受けてからさまざまな手続きが必要になります。
以下の流れを把握して、1つずつ対応していきましょう。
- 警察からの連絡
- 死亡届を提出
- 葬儀の準備
- 葬儀と火葬を行う
- 特殊清掃業者を選定する
- 特殊清掃の実施
- 賃貸契約の清算
- 遺品の整理
- 相続について検討
- 死亡後の各種手続き
以下それぞれ簡単に流れを解説します。
流れ1.警察からの連絡
まず、警察からの連絡で親族の孤独死を知るケースが多いです。
警察は孤独死の通報を受けると、まず現場検証を行います。
この際、事件性の有無を確認するため、一時的に金品や貴重品を押収しますが、事件性がなければ返還されるので、ご安心ください。
現場検証中は、遺族であっても立ち入ることはできません。
警察は、現場で発見された公的書類や契約書などから遺族を特定し、親子や兄弟など血縁関係の近い順に連絡を取るのです。
身元確認が困難な場合はDNA鑑定なども実施され、検証の結果、事件性がないと判断された場合、死体検案書とともに遺体が遺族に引き渡されます。
流れ2.死亡届を提出
警察から死体検案書を受け取ったら、速やかに役所へ死亡届を提出しましょう。
提出期限は死亡を知った日から7日以内と法律で定められています。
もし警察が死体検案書を発行しない場合は、医師による死亡診断書が必要です。
死亡診断書がないと死亡届を提出できませんので、確実に入手しましょう。
流れ3.葬儀の準備
死亡届の提出後は、葬儀の準備です。
通常の葬儀と同様、まずは喪主を決定する必要があります。
ただし、孤独死の場合は遺族が喪主になることを躊躇するケースも少なくありません。
できるだけ早めに親族間で話し合い、葬儀の規模や形式を決定しましょう。
葬儀社への連絡や日程調整など、やるべきことを整理して進めていくことが重要です。
流れ4.葬儀と火葬を行う
葬儀の日程が決まったら、その地域の慣習やルールにしたがって葬儀・火葬を執り行いましょう。
孤独死の場合、遺体の状態によっては通夜を省略するなど、通常の葬儀とは異なる対応が必要になることもあります。
流れ5.相続の検討
葬儀と火葬を行った後は、相続について検討してください。
借金や滞納家賃、未払い税金などの負債がある場合、多くの遺族が相続放棄を選択します。
ただし、相続放棄は死亡を知った日から3か月以内に手続きしなければなりません。
また、遺産を少しでも受け取ったり処分したりすると、相続放棄ができなくなるので要注意です。
流れ6.特殊清掃業者を選定する
相続について検討しつつ、特殊清掃業者を選定しましょう。
孤独死が賃貸物件で発生した場合、原状回復は義務があるため必ず特殊清掃を行います。
遺体発見時には既に腐敗が進んでいることも多く、通常の清掃では対応できない場合がほとんどです。
信頼できる特殊清掃業者を選定するため、実績や料金体系、対応の丁寧さなどを確認しましょう。
複数の業者から見積もりを取ることをおすすめします。
専門技術 × 幅広い対応!特殊清掃・カビ除去・災害復旧・お片付け清掃もおまかせください!
流れ7.特殊清掃の実施
選定した業者による特殊清掃を実施します。
清掃完了前の立ち入りは危険を伴うため、業者の許可があるまでは絶対に入室しないでください。
また、保管したい遺品がある場合は、事前に業者と相談し、誤って処分されないよう明確に伝えておくことが重要です。
流れ8.賃貸契約の清算
賃貸物件の場合、契約の清算手続きが必要です。
家賃の滞納がある場合、原則として相続人に支払い義務が発生します。
ただし、保証会社や連帯保証人がいる場合は、契約内容を確認しましょう。
特殊清掃による原状回復が完了したら、物件を明け渡し、契約を終了してください。
また、以下の記事では孤独死が起きた現場の原状回復費用の相場について解説しています。
費用を誰が支払うのか、決められている順序についても紹介しているので、併せてご確認ください。
孤独死が起きた場合の原状回復費用の相場は?内訳や誰が支払うかも解説
流れ9.遺品の整理
孤独死現場の遺品は、原則として相続人が引き取ります。
しかし、多くの場合、遺品には死臭や体液が染み込んでおり、処分せざるを得ません。
汚染されていない遺品のみを選別して引き取り、相続人間で協議して決めましょう。
流れ10.死亡後の手続き
最後に、行政手続きを漏れなく行います。
住民票の世帯主変更・介護保険の資格喪失届・年金受給の停止・光熱費に関わるライフラインの停止などの手続きをしてください。
上記の手続きを放置すると後々トラブルになる可能性があるため、チェックリストを作成するなどして、確実に対応しましょう。
2.孤独死した親族の相続で急いでやるべき3つのこと
孤独死の現場では、葬儀や清掃だけでなく「相続手続き」も早めの対応が必要です。
特に、相続人の確定や財産調査が遅れると、不要なトラブルや損失につながる可能性があります。
ここでは、孤独死が起きたあとに相続人がまず取り組むべき3つのことについて見ていきましょう。
やること1.孤独死した人の相続人を確定する
最初に行うべきは、故人の相続人を確定することです。
相続人の範囲は、民法で「配偶者」「子」「親」「兄弟姉妹」と定められており、誰が正式に権利を持つかを明確にしなければなりません。
この確定作業を怠ると、後から他の親族が権利を主張し、遺産分割や手続きが進まなくなる恐れがあるのです。
具体的には、故人の本籍地の役所で「戸籍謄本」や「除籍謄本」を取得し、家族関係を時系列で確認します。
相続人の確定ができたら、次に財産の内容を調べましょう。
やること2.プラスの財産(預金や不動産など)を調査する
相続の対象となるプラスの財産には、預貯金・不動産・生命保険・株式・自動車などがあります。
これらを正確に把握することが、今後の相続分配や税申告の基礎になるのです。
銀行口座については、通帳やキャッシュカード、郵便物を確認してください。
不動産の場合は「固定資産税納付書」や「登記簿謄本」を調べると所在や評価額が分かります。
故人が賃貸物件に住んでいた場合は、敷金や家財も資産として扱われることがあります。
特に孤独死のケースでは、管理会社や市区町村が関わることも多いため、早めに連携して情報を整理しましょう。
やること3.マイナスの財産(借金やローンなど)を調査する
プラスの財産だけでなく、借金・クレジット残高・ローンなどのマイナスの財産も必ず確認しましょう。
相続は「財産すべてを引き継ぐ」仕組みのため、借金が多い場合は相続放棄を検討する必要があるからです。
借入の有無を調べるには、郵便物・カード会社の明細・保証会社や消費者金融からの通知を確認します。
また、信用情報機関(CICやJICC)に照会することで、故人名義の借入履歴が把握可能です。
相続放棄をする場合は、相続の開始(死亡を知った日)から3か月以内に家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。
期限を過ぎると自動的に相続を承認したとみなされるため、注意が必要です。
3.親族の相続人となる人がまず最初に決めておくべき2つのこと
親族の相続人が確定したら、次に行うべきは「話し合いの準備」と「故人の住まいの扱い」を決めることです。
これらを後回しにすると、手続きが長引いたり、親族間のトラブルにつながることがあります。
ここでは、孤独死後の相続で最初に決めておくべき2つの重要なポイントを見ていきましょう。
決めること1.遺産分割協議の日程決めと協議書の作成
まず最初に、相続人全員で「遺産分割協議」を行う日程を決めましょう。
遺産分割協議とは、誰がどの財産を相続するかを話し合い、合意内容を文書にまとめる手続きのことです。
相続人全員の合意がなければ、財産は名義変更や売却ができません。
話し合いの場が持てないまま時間が経つと、預金が凍結されたままになったり、固定資産税の支払いが滞るおそれもあります。
協議がまとまったら、内容を「遺産分割協議書」として書面に残してください。
協議書には相続人全員の署名・押印が必要で、公的手続き(登記や解約)にも必ず提出します。
孤独死の場合、関係者同士が疎遠なケースも多いため、早めに日程を決めて連絡を取り合うことが重要です。
必要に応じて、行政書士や司法書士など専門家の立ち会いを依頼するとスムーズに進みます。
決めること2.故人が暮らしていた住居の扱いを決めておく
次に決めるべきことは、故人が暮らしていた「住居の扱い」です。
賃貸物件か持ち家かによって、対応方法が大きく異なります。
賃貸の場合は、契約名義人が亡くなった時点で契約は終了するため、早急に管理会社や大家へ連絡しましょう。
残された家財や荷物は、原則として相続人が責任を持って撤去しなければなりません。
この際、遺体から発生した臭いや汚染がある場合は、特殊清掃業者への依頼が必要です。
一方、持ち家の場合は、相続登記(名義変更)を行うか、売却・解体・賃貸化などの方向性を早めに話し合います。
特に空き家のまま放置すると、固定資産税の増額や近隣からの苦情につながることもあります。
相続人との間で方針を決めたら、書面やLINEなどで記録を残し、後の誤解を防ぎましょう。
また、孤独死現場のように心理的負担が大きい場合は、遺品整理士や清掃業者に任せて負担を軽減することも大切です。
4.親族の孤独死発見後に警察が行う4つのこと
親族の孤独死が発見された後、警察は主に以下の4つの手続きを行います。
- 身元の確認・現場検証
- 検死
- 死体検案書の発行
- 遺体の引き渡し
順番に詳細を見ていきましょう。
行うこと1.身元の確認・現場検証
孤独死が発見されたら、まず遺体の身元確認と現場検証が行われます。
身元確認を行い、素早く遺族へ連絡するためです。
現場検証では、遺体の状態や室内の様子、痕跡などから住人が亡くなった日時や事件性の有無を調べます。
なお現場検証の際は、警察から許可が降りるまで遺族は部屋に立ち入らないようにしましょう。
部屋の物をいじったり現場の状態を変えたりなど、警察の調査を妨げないよう指示にしたがって行動してください。
行うこと2.検死
検死は、住人が死亡した時刻や原因、事件性の有無を詳細に調べる作業です。
主に、警察医や法医学者が遺体を詳しく調べ、外傷の有無や体内の状態を確認します。
必要があれば親族や知人などへの事情聴取を受ける場合も。
故人の最近の様子や健康状態、生活環境などを把握し、死因の特定に役立てるためです。
検死は故人の尊厳を守りつつ、死因を正確に特定するため、慎重に行われます。
遺族にとっては辛い過程かもしれませんが、大切な人の最期を正確に知るための手続きだと理解して協力しましょう。
行うこと3.死体検案書の発行
死体検案書は、故人が亡くなったことを法的に証明する書類です。
警察医によって、死亡の事実・日時・場所・原因などが記載されます。
死体検案書は、火葬許可書の発行や戸籍の抹消など、遺体引き取り後の法的手続きに必要不可欠な書類です。
また、保険金の請求や相続手続きにも使用されます。
行うこと4.遺体の引き渡し
現場検証や検死が終了すると、警察から遺族へ遺体の引き渡しが行われます。
故人を最後にお見送りする準備を始めるための段階で、遺体の状態や持ち物について説明があります。
今後の手続きについての指示も受けることもあることから、気になることがあれば質問しておきましょう。
加えて、遺体の引き渡し後は取り扱いに注意が必要です。
遺体が腐敗しないように、速やかに葬儀社に連絡して適切な処置を行ってください。
また、遺体の搬送には、費用がかかることも念頭に置いておきましょう。
親族が孤独死した場合の対応や手続きについて、詳しくはこちらの記事をご参照ください。
5.親族の孤独死が起きて警察に行くときに必要な5つのもの
警察から孤独死の連絡を受けたら、すぐに警察署へ向かう必要があり、以下の5つのものを必ず用意しましょう。
- 身分証明書・印鑑
- 防寒着
- スマホの充電器
- 宿泊セット
- 遺体保管料などの費用
慌てて警察に向かうと必要なものを忘れやすいですが、遺体の引き取りから葬儀までスムーズに進めるために重要です。
(1)身分証明書・印鑑
遺体の引き取りには、引取人の身分証明書と実印が必須となります。
運転免許証やパスポートなど、顔写真付きの身分証明書を持参しましょう。
また、可能であれば故人の身分証明書も用意すると手続きがスムーズです。
印鑑は、必ずシャチハタではなく朱肉を使う実印を持参してください。
警察での手続きや死亡届の提出など、正式な書類に押印する機会が多くあります。
印鑑証明書がある場合は、併せて持参すると安心です。
証明書がないと、遺体の引き取りができない可能性もあるため、必ず確認してから出発しましょう。
(2)防寒着
警察署に行くのは普段着で問題ありませんが、遺体安置所での確認時には防寒着が必要不可欠です。
遺体安置所は遺体の腐敗を防ぐため、年間を通じて5度前後の低温に保たれています。
真夏でも室内は冷え切っているため、長袖のジャケットやカーディガンなどの防寒着を必ず持参しましょう。
また、警察署内も冷房が効いていることも多いため、防寒着があると快適に過ごせます。
(3)スマホの充電器
スマホの充電器も、必須アイテムです。
警察での手続き中、他の親族、葬儀社への連絡や相談相談、特殊清掃業者への見積もり依頼など、電話での連絡が頻繁に発生します。
また、インターネットで必要な情報を収集することも多いです。
手続きは長時間に及ぶことが多いため、充電器を忘れると途中で連絡が取れなくなる可能性も少なくありません。
(4)宿泊セット
現場が自宅から遠い場合や、手続きが長引く場合は、宿泊セットの持参を推奨します。
基本的な着替え一式に加え、洗面用具、下着類なども用意しましょう。
特に大切なのは喪服です。
遺体の引き取り後すぐに葬儀や火葬の手配が必要になる場合もあります。
通常、検死は当日中に終わりますが、その後の対応(葬儀社との打ち合わせ、特殊清掃の手配、遺品整理など)に数日かかることも珍しくありません。
慌てて自宅に戻る必要がないよう、3日分程度の着替えを用意しておくと安心です。
(5)遺体保管料などの費用
警察での手続きには、以下のような費用が必要となります。
現金での支払いが求められることが多いため、あらかじめ準備しておきましょう。
| 項目 | 費用 |
| 遺体保管料 | 2,000円(1泊あたり) |
| 検案料 | 約2万円~3万円 |
| 行政(承諾)解剖料 | 約8万円~12万円 |
| 死体検案書発行料 | 約5,000円~1万円 |
| 遺体搬送料 | 約1万2,000円~1万5,000円 |
この費用は地域や状況によって変動する可能性があります。
予備として、最大で20万円程度の現金を用意しておくと安心です。
クレジットカードが使える場合もありますが、確実を期すため現金での準備をおすすめします。
6.何が必要?親族の孤独死発見後の手続きで警察に支払う費用
孤独死が発見された後、警察の対応において遺族負担となる費用があります。
警察に支払う費用を事前に把握して、心の準備と共に金銭的な準備も整えておきましょう。
主な費用項目は以下の5つです。
- 遺体検案料
- 行政解剖料
- 死体検案書発行料
- 遺体搬送料
- 遺体保管料
各費用の詳細について見ていきましょう。
費用1.遺体検案料
遺体検案料とは、孤独死が発見された際に警察が行う検死のために必要な費用のこと。
費用は通常、2万円から3万円程度です。
主に、専門的な知識を持つ医師が遺体を詳細に調べ、死因を特定するために行われます。
外傷の有無や体内の状態を確認し、自然死なのか事故死なのか、あるいは他殺の可能性があるのかを判断するために必要な作業です。
費用2.行政解剖料
行政解剖料は、警察が必要だと判断した場合に行われる司法解剖の費用で、8万円から12万円程度かかります。
行政解剖は一見自然死に見えても、内部に不自然な損傷がある場合や、犯罪性の疑いが完全に否定できない場合などに行われる作業です。
行政解剖により、故人の死因が分かり、遺族の疑問や不安を解消できます。
また、社会的な観点からも、潜在的な犯罪を見逃さないための手続きです。
費用3.死体検案書発行料
死体検案書発行料は、警察医が作成する公的な死亡証明書を発行してもらうための費用です。
故人の死亡を法的に証明して、火葬許可証の発行や相続手続き、保険金などの手続きを進めるために発行されます。
なお死体検案書の発行には、5,000円から1万円程度必要です。
費用4.遺体搬送料
遺体搬送料は、孤独死の現場から警察署や病院の霊安室まで、遺体を運ぶ際にかかる費用です。
通常、10km以内の基本料金相場で1万2,000円から1万5,000円程度かかります。
ただし深夜や早朝、休日に搬送する場合は追加料金がかかることも少なくありません。
費用5.遺体保管料
遺体保管料は、警察で引き取られた遺体を、一時的に保管する際にかかる費用です。
遺体保管料の目安は、専用の冷蔵設備や管理スタッフの人件費などを含めて1泊あたり2,000円程度。
遺族が遠方で過ごしており即座に引き取りに来られない場合や、検死や解剖の結果を待つ場合などに遺体は一時的に保管されます。
また、以下の記事では特殊清掃にかかる費用の詳細や内訳について、詳しく解説しているので、合わせてご確認ください。
孤独死の特殊清掃費用はいくらくらい?費用の相場や誰が負担するのか解説します
7.親族の遺体の引き取りを拒否した場合の費用負担について
孤独死した親族とは長年疎遠だった、経済的に余裕がないなどの理由で、遺体の引き取りを拒否したいと考える場合、警察にその旨を伝えることができます。
しかし、親族の遺体の引き取りを拒否しても、費用負担が完全になくなるわけではありません。
通常、遺体を引き取る人がいない場合、自治体が火葬を手配し、無縁仏として供養されます。
しかし、自治体が負担するのは最低限の火葬や埋葬に限られており、遺体の搬送費や遺品整理、特殊清掃などの費用は、原則として相続人に請求される可能性があります。
また、相続人が相続放棄をした場合でも、扶養義務者がいる場合は、その方に費用請求がいくこともあります。
例えば、故人の財産が不足している場合、相続人に火葬や埋葬の費用が請求されることがあります。さらに、孤独死による遺体の損傷が激しく、特殊清掃が必要な場合は、その費用を誰が負担するのかが問題になります。
住居の所有者(故人・家族・賃貸の大家)によって負担の範囲が異なり、場合によっては数十万円以上の費用が発生することもあります。
このように、遺体の引き取りを拒否することは可能ですが、結果として費用が発生し、相続人や扶養義務者に請求されるケースもあるため、事前に自治体や法律の専門家に相談することをおすすめします。
8.親族の孤独死後に起こりやすいトラブルとその回避方法
続いて、孤独死が発生したあとに起きがちなトラブルとその対策について紹介します。
孤独死の後には、費用負担の誤解や親族間の意見対立、悪質業者による高額請求など、遺族が直面しやすいトラブルが発生しがちです。
この内容を知らなければ、思わぬ高額請求を受けたり、親族間の関係が悪化したり、解決に時間と労力を浪費するリスクがあります。
1つずつ、見ていきましょう。
トラブル1.費用負担に関する誤解
孤独死にかかる費用を誰が負担するのかを明確にしておくことで、後からの誤解や請求トラブルを避けやすいです。
遺体搬送・検案料・葬儀費用・特殊清掃などは、状況により負担者が異なります。
相続人や連帯保証人が費用請求を受けるケースが多く、認識に差があるとトラブルになりやすいです。
実際に、兄弟間で「葬儀費用は全員で分担すると思っていたが、自分だけに請求が来た」と揉めた事例があります。
相続放棄をすれば費用負担を免れる一方、遺産も一切受け取れなくなるため、判断が重要です。
請求の範囲と相続の関係を理解し、早めに弁護士や行政に確認することで、費用負担に関する誤解を防げます。
トラブル2.親族間での揉め事
孤独死後の対応では、親族間での意思疎通を徹底することがトラブル防止につながります。
葬儀の形式や費用分担、遺骨や遺品の扱いは感情が絡みやすく、事前に合意が取れていないと対立が起きやすいからです。
例えば、遺骨を誰が引き取るかを巡って「自分が保管するべきだ」と主張が対立し、家庭裁判所に持ち込まれたケースもあります。
費用面でも「自分は負担したくない」と不公平感が生まれると関係が悪化するでしょう。
重要な判断は複数人で共有し、書面やメッセージで記録を残すことで、後からの言い分の食い違いを防げます。
トラブル3.業者間との揉め事
特殊清掃や葬儀の業者は、複数社を比較し信頼できる会社を選ぶことが重要です。
悪質な業者に依頼すると高額請求や作業の不備が発生し、再度依頼が必要になって余計な費用と時間がかかります。
「基本料金5万円」と安く提示して契約させ、作業後に消臭・害虫駆除費用を別途請求し、最終的に30万円以上になった例も耳にすることが多いです。
業者との契約前に見積もりの内訳や追加費用の有無を確認し、口コミや実績を調べましょう。
そうすることで、業者選びの失敗を防ぎやすくなります。
9.特殊清掃業者を選ぶ際のポイント

最後に、特殊清掃業者の選び方について紹介します。
良い業者の選び方を知っておけば、適正な価格でしっかりと作業を行ってもらえる可能性が高くなるでしょう。
ポイントは以下の3点です。
- 技術力や許可の有無を確認する
- 料金体系が明確で適正かどうか
- 遺品整理や消臭など関連サービスに対応できるか
1つずつ、見ていきましょう。
ポイント1.技術力や許可の有無を確認する
特殊清掃を依頼する際は、技術力と必要な許可を持つ業者を選ぶことが重要です。
特殊清掃は通常の掃除と異なり、血液や体液の除去、消臭、消毒など高度な専門知識と技術が求められます。
さらに、孤独死現場の汚染物や大量の生活ゴミも「一般廃棄物」に該当するため、正規の許可を持つ業者しか処理できません。
もし無許可業者が収集して不法投棄した場合、後から依頼者が関与を疑われるケースがあります
一方で、特殊清掃の専門資格や豊富な実績を持つ業者なら、安心して作業を任せられるでしょう。
技術力や許可を持つ信頼できる業者に依頼することが、確実かつ安全に清掃を進めるための必須条件です。
ポイント2.料金体系が明確で適正かどうか
業者を選ぶ際は、料金体系が分かりやすく適正であるかを必ず確認しましょう。
特殊清掃は現場の状況によって費用が変動しやすく、不明瞭な見積もりでは作業後に高額請求を受けるリスクがあるからです。
例えば「基本料金5万円」とだけ提示し、作業後に消臭や害虫駆除の追加費用を請求する悪質業者も存在します。
一方、優良業者は作業内容ごとの料金を事前に明示し、追加料金が発生する場合も詳細に説明することが多いです。
料金の内訳を丁寧に説明する業者を選ぶことで、トラブルを避けて安心して依頼できます。
ポイント3.遺品整理や消臭など関連サービスに対応できるか
特殊清掃と合わせて遺品整理や消臭など関連サービスに対応できる業者を選ぶことをおすすめします。
孤独死現場では、清掃だけでなく遺品整理や徹底的な脱臭、場合によっては原状回復工事まで必要になることが多いからです。
これらを一括で任せられる業者なら、複数の業者を探す手間が省け、作業の質も統一されます。
このように、遺品整理や消臭まで対応可能な業者を選ぶことで、時間・費用・労力を大幅に削減できるのです。
孤独死の連絡が警察から来たら必要な費用を準備しましょう
孤独死の発見は、遺族にとって心理的にも経済的にも大きな負担となるでしょう。
しかし、事前に必要な手続きや費用を理解しておくことで、いざという時に冷静に対応できます。
いざという時に混乱を最小限に抑えながら対応するためにも、家族や親族と事前に話し合い、緊急時の対応計画を立てておくことが重要です。
もし突然の出来事で判断が難しい状況に直面した場合には、無理をせず、私たちSpread株式会社にご相談ください。
特殊清掃の専門家として、誠実に、迅速にサポートいたします。
本記事が、突然の出来事に直面した際の指針となり、少しでも心の支えになることを願っています。
専門技術 × 幅広い対応!特殊清掃・カビ除去・災害復旧・お片付け清掃もおまかせください!
また、以下の記事では、私たちSpread株式会社のコラムにある「特殊清掃」に関する話題をまとめています。
孤独死や火災・水害の清掃、消臭など、さまざまな内容を紹介中です。
他にも特殊清掃に関する悩みがあれば、こちらの記事をチェックすると解決のヒントが見つけられますよ。